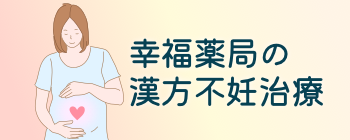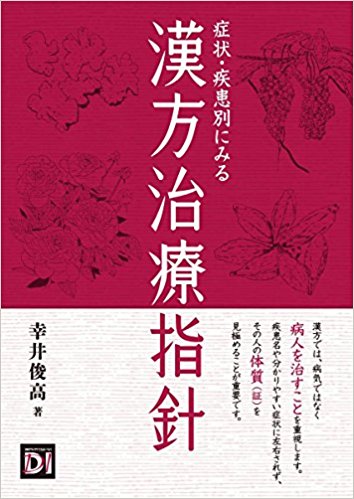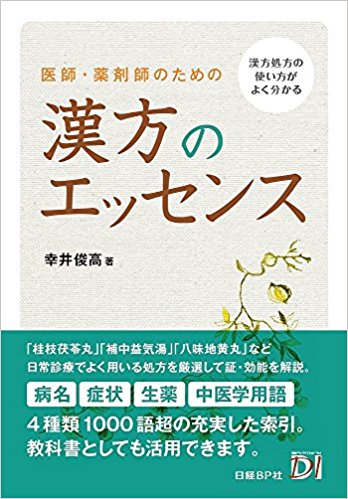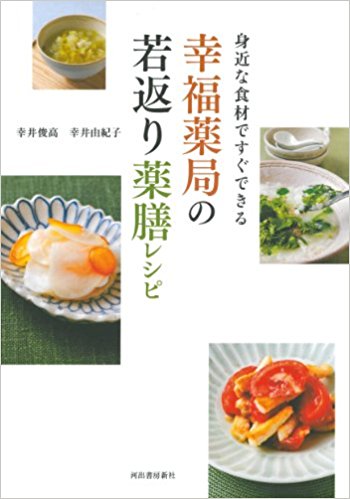冷え症の症例
(こちらの記事の監修:中医師 幸井俊高)
薬石花房 幸福薬局 の漢方薬で冷え症が治った症例
こちらは症例紹介ページです。冷え症の解説ページは こちら へどうぞ
■症例1「冷え症です。下腹部、それに手足が冷えます。お腹が冷えるせいか、便は軟らかく、よく下痢をします」
疲れやすく、元気もあまりありません。食欲不振で、少し食べればすぐお腹が一杯になります。舌は白っぽく、白い舌苔がついています。
この人は「熱をつくる機能が弱い体質」です。漢方では「脾胃陽虚」証といいます。五臓の脾と六腑の胃、つまり胃腸の消化吸収機能が弱いため、なかなか飲食物を熱に変えることができません。おなかが冷える、軟便、下痢、食欲不振、舌が白い、などはこの証の特徴です。
この証に対しては、胃腸の機能を高める漢方薬で、冷え症体質を改善します。胃腸の消化吸収能力を補い、熱をつくる機能を高める漢方薬を服用し、1カ月で手足が温かくなるのを感じ始めました。その後も1年間ほど飲み続け、軟便や食欲不振も解消させました。
■症例2「冬の寒さや夏の冷房が苦手です。ちょっと寒さを感じるだけで、すぐ手足の先が冷たくなります」
小さい頃は、しもやけができていました。手足のほかに、太ももの内側も冷えます。顔色につやがなく、くすみがちです。目が疲れやすく、すぐ乾燥します。肌も乾燥しがちです。生理痛が激しいのも悩みの種です。白っぽい色の舌をしています。
この女性「熱を体の隅々に運ぶ機能が弱い体質」のひとつである「血虚(けっきょ)」証です。体内を循環する血液量が少ない体質です。ちょっとした寒冷刺激で血行が滞り、体温が行き渡らなくなり、冷え症になります。
この体質の場合は、漢方薬で血を補い、血行を促進して体を温めます。3カ月ほどでずいぶん冷えが解消されました。半年後には生理痛も気にならなくなりました。
「熱を体の隅々に運ぶ機能が弱い体質」は、ほかにもタイプがあります。「血瘀(けつお)」証と「気滞(きたい)」証です。
血瘀証は、血液の流れが悪い体質です。血行が停滞するために体温が体の隅々にまでスムーズに運ばれず、冷え症になります。特に下半身の冷えや、冷えのぼせがみられます。顔や唇の色が暗く、シミができやすい体質でもあります。
この証の場合は、血流をさらさらにする漢方薬で冷え症体質を改善します。
気滞証は、気の流れが悪い体質です。気の働きのひとつである推動作用がスムーズでないために、血液循環を滞りなくサポートすることができず、体が冷えてしまいます。特に手足の末端が冷えます。緊張、いらいら、頭痛、腹部膨満感などの症候が同時にみられます。
この証の人には、気の流れをのびやかにする漢方薬を用います。
■症例3「小さい頃から寒がりです。冷えるせいか、トイレが近いです」
38歳の女性です。疲れやすく、足腰が冷えてだるさを感じます。トイレでは毎回透明に近い色の尿がたくさん出ます。冷たい飲み物はあまり好きではありません。冬は厚着をしており、暖房器具は秋口から必需品です。舌は白っぽくて、湿り気のある舌苔がついています。お子さんに恵まれず、ご主人と二人暮らしです。
この女性は「熱を蓄えておく機能が弱い体質」で、漢方では腎虚(じんきょ)証というタイプです。腎は五臓のひとつで、生きるために必要なエネルギーや栄養を貯蔵しているところです。その腎が弱いため、冷え症体質になっています。寒がり、腰から下が冷える、だるさ、トイレが近いなどは、腎虚の特徴です。熱を蓄えておく機能が弱い体質に相当します。
この証の場合は、漢方薬で腎を補い、冷え症を治します。この女性も冷え症が少しずつ緩和され、1年後に妊娠しました。
(こちらの記事は「薬石花房 幸福薬局」幸井俊高が執筆・監修しました。日経DIオンラインにも掲載)
*執筆・監修者紹介*
 幸井俊高 (こうい としたか)
幸井俊高 (こうい としたか)
東京大学薬学部卒業。北京中医薬大学卒業。中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。「薬石花房 幸福薬局」院長。『医師・薬剤師のための漢方のエッセンス』『漢方治療指針』(日経BP)など漢方関連書籍を25冊以上執筆・出版している。日本経済新聞社の医師・薬剤師向けサイト「日経メディカル(日経DI)」や「日経グッデイ」にて長年にわたり漢方コラムを担当・連載・執筆。中国、台湾、韓国など海外での出版も多い。17年間にわたり帝国ホテル東京内で営業したのち、ホテルの建て替えに伴い、現在は東京・銀座で営業している。
あなたに合った漢方薬が何かは、あなたの証(体質や病状)により異なります。自分に合った漢方薬を選ぶためには、正確に処方の判断ができる漢方の専門家に相談することが、もっとも安心で確実です。どうぞお気軽にご連絡ください。