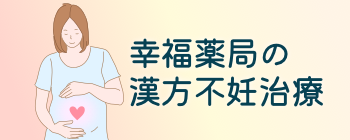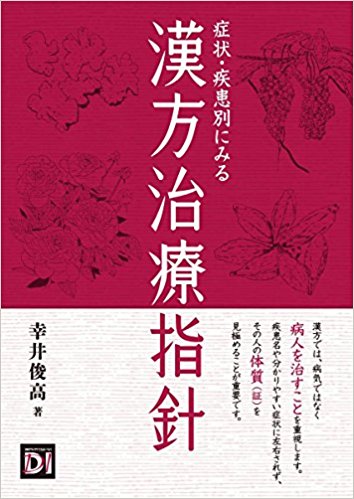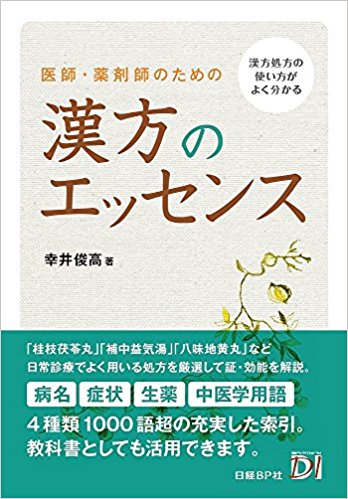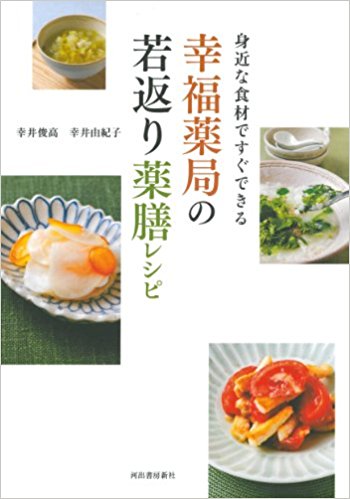イライラが改善した症例
(こちらの記事の監修:中医師 幸井俊高)
薬石花房 幸福薬局 の漢方治療で「イライラ」が改善した症例
性格とあきらめずにご相談ください。
こちらは症例紹介ページです。イライラの解説ページは こちら へどうぞ
■症例1「会社で自分の思うように仕事が運ばず、職場の人間関係もぎくしゃくしており、かなりイライラしています。あせりを感じ、いても立ってもいられない感じになることもあります」
帰宅しても、なにかあるとすぐ会社のことが思い出され、ときに動悸がしたり胸苦しくなったり、不安感にさいなまれたりします。夜もなかなか寝つけません。夢をよく見ます。口の渇きがあり、赤い舌をしています。
この人の証は「心火」です。意識や思考、心など、心神をつかさどる五臓の「心」の機能が亢進して興奮し、火熱として燃えさかっている状態です。
上記の症状は、すべて心火証によくみられるものです。中枢神経系や自律神経系が失調し、過亢進し、イライラする、じっとしていられない、あせりを感じる、などの症状が生じています。
顔面紅潮や、目の充血、口臭、口内炎などがみられることもよくあります。
この証の人に対しては、心火を冷ます漢方薬を使います。この人は漢方薬を服用し、2カ月ほどでイライラから解放され、夜もぐっすり眠れるようになりました。
似たような症状でも、便秘をともなう場合や、疲れやすいなどの症候をともなう場合など、さらに状態を見極めて漢方薬を使い分けます。
は清心蓮子飲(せいしんれんしいん)を用います。いずれの処方名にも、心火の「心」の字が入っています。
■症例2「このところ、すぐイライラするようになりました。こんなことでイライラしなくてもいいのに、と落ち込むこともよくあります。特に生理前にひどくなります」
イライラしているときは食欲もなくなり、胸苦しくなります。すっきり排便せず、便秘と下痢を繰り返します。生理前には胸の張りなどの症状が強く現れます。舌は淡紅色です。
この女性の証は「肝鬱(かんうつ)」です。肝気鬱結(かんきうっけつ)ともいいます。五臓の「肝」の気の流れが鬱滞し、小さな刺激に対しても敏感に反応しやすい体質になっています。ストレスや環境変化を大げさに受け止めてしまうタイプです。
イライラが一番の悩みのようですが、落ち込むことも多く、情緒が不安定になっているのでしょう。肝気鬱結の特徴です。無口になる、ため息をつく、といった症状が現れる場合もあります。
こういう場合は、肝気の鬱結を和らげる漢方薬で、イライラしやすい体質を改善していきます。漢方薬を服用して半年以上かかりましたが、この女性も“あまりイライラしない体質”になりました。
■症例3「年齢とともに、イライラしやすくなってきました。怒らなくてもいいほどのちょっとした部下のミスにもイライラし、叱ってしまうこともあります」
やはり年齢的なものかもしれませんが、寝汗をかくようになりました。夢にうなされて夜中に起きると寝汗をびっしょりかいていることもあります。
のぼせや手足のほてりもあり、布団から手足を出して寝ています。のどがよく渇き、冷たい水をよく飲みます。舌は赤く、舌苔がほとんどついていません。
この男性の証は「陰虚火旺(いんきょかおう)」です。体内にこもる過剰な火熱を冷ますのに必要な陰液が不足している体質です。同じ強さの火熱でも、強くからだに影響してきます。したがって、普通ならイライラしない些細なことにも反応しやすくなっており、イラ立ちます。足腰がだるい、めまい、耳鳴りといった症状を伴う場合もあります。
こういう場合は、陰液を補う漢方薬で体質を改善します。
(こちらの記事は「薬石花房 幸福薬局」幸井俊高が執筆・監修しました。日経DIオンラインにも掲載)
*執筆・監修者紹介*
 幸井俊高 (こうい としたか)
幸井俊高 (こうい としたか)
東京大学薬学部卒業。北京中医薬大学卒業。中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。「薬石花房 幸福薬局」院長。『医師・薬剤師のための漢方のエッセンス』『漢方治療指針』(日経BP)など漢方関連書籍を25冊以上執筆・出版している。日本経済新聞社の医師・薬剤師向けサイト「日経メディカル(日経DI)」や「日経グッデイ」にて長年にわたり漢方コラムを担当・連載・執筆。中国、台湾、韓国など海外での出版も多い。17年間にわたり帝国ホテル東京内で営業したのち、ホテルの建て替えに伴い、現在は東京・銀座で営業している。
あなたに合った漢方薬が何かは、あなたの証(体質や病状)により異なります。自分に合った漢方薬を選ぶためには、正確に処方の判断ができる漢方の専門家に相談することが、もっとも安心で確実です。どうぞお気軽にご連絡ください。
関連する記事を読む
- イライラ (病気・症状)