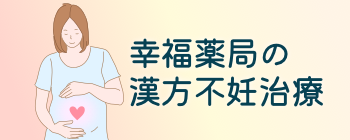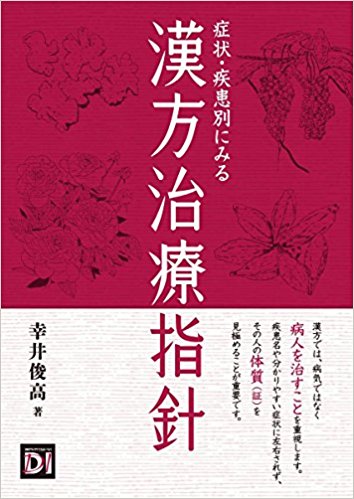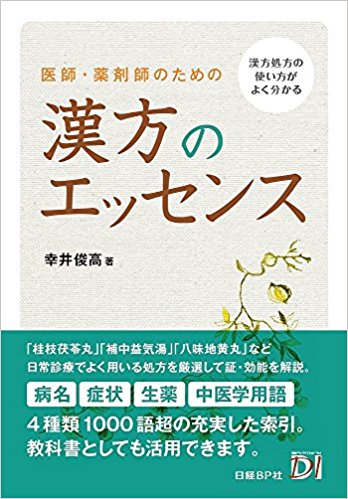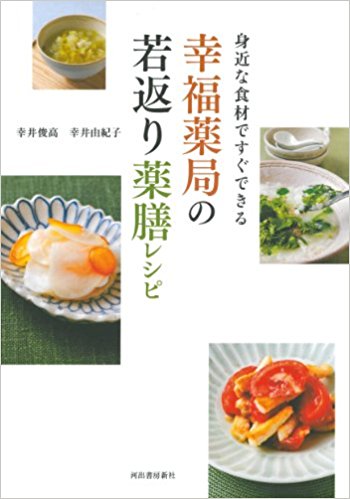歯周病の症例
(こちらの記事の監修:中医師 幸井俊高)
薬石花房 幸福薬局 の漢方薬で歯周病が改善した症例
こちらは症例紹介ページです。歯周病の解説ページは こちら へどうぞ
■症例1「最近、冷たい水を飲むと歯にしみるようになりました。歯を磨くと歯茎から血が出ることもあります。歯医者さんで診てもらい、歯周病と言われました」
朝起きると、口の中が粘ついています。口臭が気になります。疲れると歯茎がはれて、歯が浮くように感じることもあります。舌をみると赤く、その上に黄色い舌苔がついています。
この人の証は「胃熱」です。胃から上の消化器官で炎症を起こしやすい体質です。熱邪が胃の機能を阻害して口の中に上昇し、歯周病を生じています。口臭、赤い舌、黄色い舌苔は、この証の特徴です。口内炎ができやすい、のどが渇く、といった症状もよくみられます。
この証の人に対しては、胃熱を冷ます漢方薬を使います。この人の場合は、胃熱を冷まし、さらに胃腸機能を調える漢方薬を服用して2カ月ほどで炎症が治りました。口臭も気にならなくなりました。
■症例2「長年、歯周病に悩まされています。歯医者さんに通っているのですが、なかなか治りません。唾液の量が少ないのが原因だと言われました」
仕事の関係で疲れがたまったときや、緊張が続くときに、胃が重くなり、歯周病が悪化します。口内炎もできます。
「唾液には殺菌作用があるのだが、あなたの場合、唾液が少ないので歯周病菌がなかなか減らない」と歯医者さんは言います。舌は深赤色をしており、舌苔がほとんどついていません。
この人の証は「胃陰虚」です。疲労、緊張、ストレス、暴飲暴食などによる胃への負担などが長引くと、次第に体液などの陰液が消耗し、この証になります。
陰液が少ない体質なので熱を冷ます機能が弱く、その結果、相対的に熱が余ることになり、それが熱邪となって口の中で炎症を引き起こします。
なお五臓六腑の「胃」は単なる解剖学的な胃ではなく、口腔内を含め広く消化器官を指します。
この体質の場合は、胃の陰液を補う漢方薬で、歯周病ができやすい体質を改善します。
この人は漢方薬を服用することにより次第に唾液の分泌量が増え、3カ月後には歯周病の病巣が小さくなり始め、9カ月後に病巣は完全になくなりました。陰液が補われ、免疫力が高まったのでしょう。
■症例3「歯医者さんに通っているのですが、歯周病が根治しません。もともと疲れやすく、かぜをひきやすいので、免疫力が弱いのが根本的な原因かと思っています」
昔から胃腸が弱く、なにかあるとすぐ食欲がなくなります。便は軟らかめで、よく下痢をします。疲れるとすぐ口内炎ができます。だるさや立ちくらみを感じることもあります。舌は白っぽい色をしています。
この人は「脾気虚」証です。消化吸収機能が弱く、免疫力が低下しています。
気が不足すると諸機能が衰えるため、熱をコントロールする機能が弱くなり、炎症が生じやすくなります。その結果、歯周病菌の勢いがなかなか弱まらず、歯周病が根治できません。
こういう場合は漢方薬で脾気を補うことにより、歯周病の治療を進めます。この人は漢方薬を服用して6カ月目くらいから、ようやく歯周病の病巣が小さくなってきました。少しずつ疲れにくくなり、かぜもひかなくなってきました。
(こちらの記事は「薬石花房 幸福薬局」幸井俊高が執筆・監修しました。日経DIオンラインにも掲載)
*執筆・監修者紹介*
 幸井俊高 (こうい としたか)
幸井俊高 (こうい としたか)
東京大学薬学部卒業。北京中医薬大学卒業。中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。「薬石花房 幸福薬局」院長。『医師・薬剤師のための漢方のエッセンス』『漢方治療指針』(日経BP)など漢方関連書籍を25冊以上執筆・出版している。日本経済新聞社の医師・薬剤師向けサイト「日経メディカル(日経DI)」や「日経グッデイ」にて長年にわたり漢方コラムを担当・連載・執筆。中国、台湾、韓国など海外での出版も多い。17年間にわたり帝国ホテル東京内で営業したのち、ホテルの建て替えに伴い、現在は東京・銀座で営業している。
あなたに合った漢方薬が何かは、あなたの証(体質や病状)により異なります。自分に合った漢方薬を選ぶためには、正確に処方の判断ができる漢方の専門家に相談することが、もっとも安心で確実です。どうぞお気軽にご連絡ください。
関連する記事を読む
- 歯周病 (病気・症状)