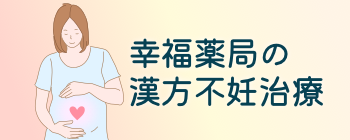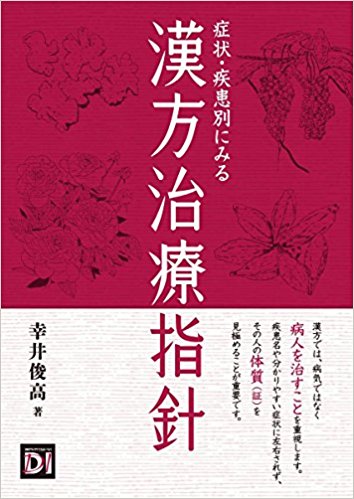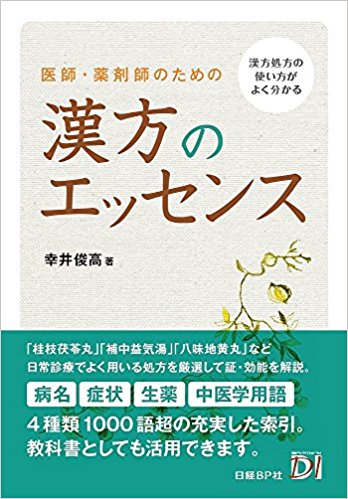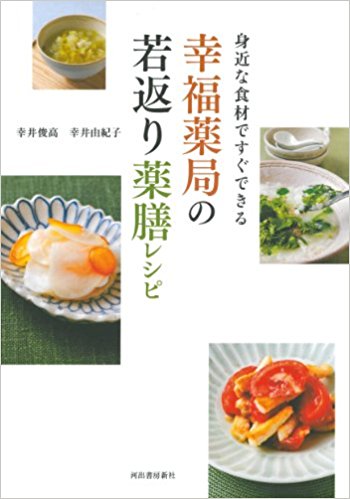脳梗塞の症例
(こちらの記事の監修:中医師 幸井俊高)
薬石花房 幸福薬局 の漢方薬で脳梗塞に効果があった症例
こちらは症例紹介ページです。脳梗塞の解説ページは こちら へどうぞ
■症例1「2年前に脳梗塞で倒れました。それ以来リハビリをしています。少しずつ改善していますが、話し言葉を明瞭に発音できない後遺症(構音障害)が残っています」
構音障害も最初の頃より改善されていますが、まだ以前のようには話せません。話していることが相手に伝わらないときなどは、いらいらしてしまいます。驚きやすいところもあります。
眠りが浅く、朝早く目が覚めます。痰がたくさん出ます。舌を出してもらうと、細かくふるえていました。舌にはべっとりとした黄色い舌苔が付着していました。
この人の証は、「痰迷心竅(たんめいしんきょう)」です。心は五臓のひとつで、血脈をつかさどること(心臓を含めた血液循環系の維持)と、神志をつかさどること(人間らしい高次の精神活動の遂行)が、そのおもな機能です。
このうちの、神志をつかさどる機能が痰によって阻害されてこの証となり、脳梗塞になったと考えられます。
いらいらしやすい、驚きやすい、眠りが浅い、朝早く目が覚める、痰が多い、舌がふるえる、べっとりとした黄色い舌苔などは、この証の特徴です。
ひとりごと、情緒不安定、知覚麻痺、動悸、口の中が粘る、などの症状がみられることもあります。
この証の場合は、漢方薬で痰飲を除去し、開竅することにより、脳梗塞の後遺症の緩和や再発防止、予防に当たります。
この患者さんに漢方薬を服用してもらったところ、2か月後には、口や舌が動かしやすくなってきて、話しやすくなってきたように思うとのことでした。10か月後くらいになると、まだ以前ほど早くは話せませんが、ずいぶん話しやすくなり、いらいらしなくなりました。
■症例2「去年脳梗塞になって以来、忘れっぽくなりました。脳血管性認知症と診断されています」
物忘れのほかには、気力が大きく低下しました。何もやる気が起きません。家でごろごろすることが多くなりました。手足のしびれや痙攣があります。舌は深紅色で、舌苔はあまり付着していません。
この患者さんは、「肝腎陰虚(かんじんいんきょ)」証です。肝は五臓のひとつで、からだの諸機能を調節し、情緒を安定させる働き(疏泄:そせつ)を持ちます。
腎も五臓のひとつで、生きるために必要なエネルギーや栄養の基本物質である精(せい)を貯蔵し、人の成長・発育・生殖をつかさどります。
これら肝と腎の陰液が不足している体質が、この証です。加齢に伴い生じる脳梗塞と深い関係にある証です。
この体質の場合は、肝腎の陰液を補う漢方薬を使います。この患者さんに漢方薬を服用してもらったところ、3か月後になると、自ら進んで散歩をするようになってきました。笑顔が増えました。
5か月後には、自分から話すことも増え、快活になってきました。服用を始めて1年後には物忘れもある程度改善されてきています。
■症例3「脳梗塞の再発を繰り返しています。ここ4年の間に3度体調の不調が生じ、脳梗塞と診断されました。今のところ軽度の脳梗塞とのことですが、再発のたびに症状が重くなると聞き、心配です。再発しないようにできればと思います」
現時点でのおもな後遺症は、軽度の感覚障害です。痛みや温度に対する感覚がやや鈍く、手足のしびれがあります。舌は淡白色でぽってりとしており、白い舌苔が付着しています。
この患者さんの証は、「気虚血瘀(ききょけつお)」です。気虚と血瘀の二つの証が同時に生じている状態です。脳の機能低下(気虚)や脳の血管障害(血瘀)が関与して、脳梗塞になったものと思われます。
手足のしびれ、ぽってりとした淡白色の舌、白い舌苔などは、この証の特徴です。手足に力が入らない、舌がこわばる、尿失禁などの症状がみられることもあります。
この体質の場合は、漢方薬で足りない気を補い、血行を促進し、脳梗塞の再発防止や後遺症の緩和、予防をします。この患者さんは漢方薬の服用を始めて3年になりますが、脳梗塞の再発はせずに過ごせています。
(こちらの記事は「薬石花房 幸福薬局」幸井俊高が執筆・監修しました。日経DIオンラインにも掲載)
*執筆・監修者紹介*
 幸井俊高 (こうい としたか)
幸井俊高 (こうい としたか)
東京大学薬学部卒業。北京中医薬大学卒業。中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。「薬石花房 幸福薬局」院長。『医師・薬剤師のための漢方のエッセンス』『漢方治療指針』(日経BP)など漢方関連書籍を25冊以上執筆・出版している。日本経済新聞社の医師・薬剤師向けサイト「日経メディカル(日経DI)」や「日経グッデイ」にて長年にわたり漢方コラムを担当・連載・執筆。中国、台湾、韓国など海外での出版も多い。17年間にわたり帝国ホテル東京内で営業したのち、ホテルの建て替えに伴い、現在は東京・銀座で営業している。
あなたに合った漢方薬が何かは、あなたの証(体質や病状)により異なります。自分に合った漢方薬を選ぶためには、正確に処方の判断ができる漢方の専門家に相談することが、もっとも安心で確実です。どうぞお気軽にご連絡ください。
関連する記事を読む
- 脳梗塞の漢方治療(予防・後遺症の緩和・再発防止) (病気・症状)