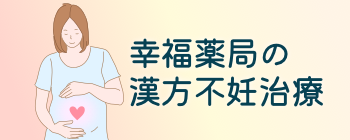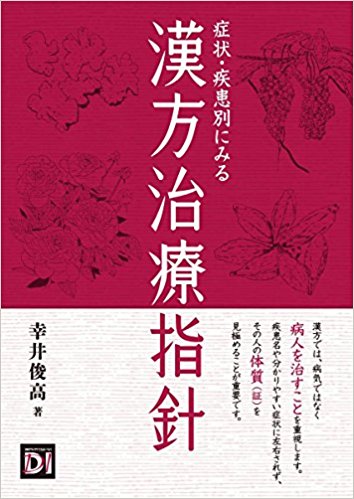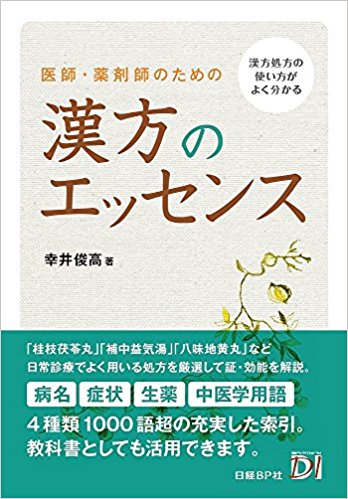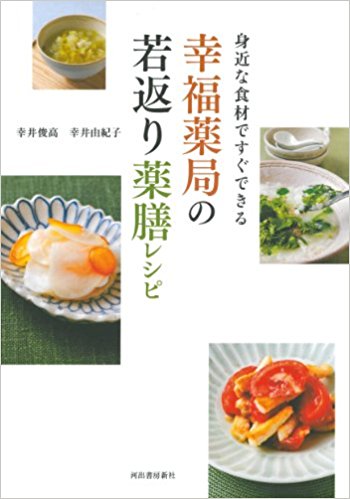気管支炎
(こちらの記事の監修:中医師 幸井俊高)
気管支炎が治った − 漢方で気管支炎が生じた根本原因を排除
こちらのページでは、気管支炎の漢方治療について解説します。当薬局では、気管支炎の根本原因となる病邪を除去することにより、気管支炎の根本治療を進めます。
*目次*
気管支炎とは
症状
原因
治療
治療(気管支炎の漢方治療)
体質別の漢方治療方針
よく使われる漢方薬
予防/日常生活での注意点
(症例紹介ページもあります)
気管支炎とは
気管支炎は、気管支に炎症が生じ、咳や痰などの症状を引き起こす疾患です。短期間で治る急性気管支炎と、長期にわたり症状が長引く慢性気管支炎とがあります。喫煙や受動喫煙により、症状が悪化したり慢性化したりします。
症状
よくみられる症状には、咳嗽、痰、発熱、喘鳴、息切れ、呼吸困難、全身倦怠感などがあります。喉の痛みや、鼻水、チアノーゼ症状などが生じることもあります。長期化して気管支喘息や肺炎に移行する場合もあります。
原因
急性気管支炎の多くは、インフルエンザなどのウイルスや細菌、マイコプラズマによる感染症が原因で起こります。慢性気管支炎は、抗酸菌や緑膿菌などによる感染症や、喫煙、受動喫煙、大気汚染などが原因で起こります。
治療
つらい症状を早く緩和させたい場合は西洋医学、根本的に治療して慢性化した気管支炎を治したい場合などは漢方が適しています。
西洋医学では、鎮咳薬や去痰薬などの対症療法が中心に治療が行われます。病原菌の関与がある場合は抗生物質が用いられます。症状が重い場合は、気管支拡張薬が使われる場合もあります。
治療(気管支炎の漢方治療)
漢方では、気管支炎を五臓の肺や痰飲(たんいん)と関係が深い疾患と捉えています。
五臓の肺のおもな機能(肺気)は、呼吸により空気中から必要な成分(酸素など)を吸入し、体内の不要物(二酸化炭素など)を排出することです。これを「肺は気をつかさどる」といいます。この肺の機能が失調すると、気管支炎になります。
また痰飲とは、津液(しんえき:体内の水液)が水分代謝の失調などにより異常な水液と化した病理産物です。痰飲が咳嗽や痰となって表れると、気管支炎になります。
したがって漢方では、五臓の肺の機能をととのえたり、痰飲を除去したりして、気管支炎を治療します。
(症例紹介ページもあります)
体質別の漢方治療方針
漢方では、患者一人一人の体質に合わせて、五臓の肺の機能をととのえたり、痰飲を除去したりして、気管支炎を治療します。以下に、気管支炎にみられることの多い証(しょう)と漢方薬を紹介します。証とは、患者の体質や病状のことです。患者一人一人の証(体質や病状)に合わせて処方を決め、治療を進めるのが漢方治療の特徴です。
- ①肺熱
咳嗽のほかに、黄色く粘稠な痰が出るようなら、「肺熱(はいねつ)」証です。五臓の肺に熱邪が侵入するとこの証になり、炎症を起こし、気管支炎になります。口渇、胸の熱感、鼻づまり、後鼻漏もみられます。肺熱を除去する漢方薬で炎症を冷まし、気管支炎を治療します。
- ②寒痰
激しい咳嗽と、喀痰しやすい薄い痰がみられるようなら、「寒痰(かんたん)」証です。寒痰は、痰飲が寒邪と結びついたものです。喘息のようにゼイゼイ喉元で音が鳴ることや(喘鳴)、息切れが生じる場合もあります。漢方薬で寒痰を除去し、気管支炎を治療します。
- ③痰飲
咳を繰り返し、痰の量が多いようなら、「痰飲(たんいん)」証です。痰飲は、体液代謝の失調や低下、炎症、循環障害、ホルモン異常、代謝産物の体内蓄積、暴飲暴食、食事の不摂生、運動不足などによって生じます。痰飲を取り除く漢方薬を用い、気管支炎の治療にあたります。
- ④肝鬱気滞
自律神経の失調や更年期障害と関与していそうな場合は、「肝鬱気滞(かんうつきたい)」証が多くみられます。からだの諸機能を調節し、情緒を安定させる働きを持つ五臓の肝の機能(肝気)がスムーズに働いていない体質です。肝は自律神経系と関係が深く、自律神経の失調が気管支に及ぶと、気管支炎になります。漢方薬で肝気の鬱結を和らげて肝気の流れをスムーズにし、気管支炎を治していきます。
- ⑤肺陰虚
乾燥した咳嗽が出て、咳き込むことが多く、痰がからんでなかなか切れないようなら、「肺陰虚(はいいんきょ)」証です。五臓の肺の陰液(肺陰)が不足している体質です。肺陰は、肺や気道の分泌液や組織液として肺を滋潤し栄養を与えますが、慢性疾患や炎症により津液が消耗すると、この証になります。血痰、喉の乾燥、口渇などの症状がみられます。ときに吐きそうになるくらい咳き込むことや、嗄声(声枯れ)が生じる場合もあります。漢方薬で肺の陰液を補い、気管支炎を治します。
ほかにも気管支炎にみられる証はたくさんあります。証が違えば薬も変わります。自分の証を正確に判断するためには、漢方の専門家のカウンセリングを受けることが、もっとも確実で安心です。
よく使われる漢方薬
- ①麻杏甘石湯など
咳嗽のほかに、黄色く粘稠な痰が出るようなら、たとえば、麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう)など、「肺熱(はいねつ)」証を治療する漢方薬を用います。
- ②小青竜湯など
激しい咳嗽と、喀痰しやすい薄い痰がみられるようなら、たとえば、小青竜湯(しょうせいりゅうとう)など、「寒痰(かんたん)」証を治療する漢方薬を使います。
- ③温胆湯など
咳を繰り返し、痰の量が多いようなら、たとえば、温胆湯(うんたんとう)など、「痰飲(たんいん)」証を治療する漢方薬を用います。
- ④滋陰至宝湯など
自律神経の失調や更年期障害と関与していそうな場合は、たとえば、滋陰至宝湯(じいんしほうとう)など、「肝鬱気滞(かんうつきたい)」証を治療する漢方薬を使います。
- ⑤滋陰降火湯など
乾燥した咳嗽が出て、咳き込むことが多く、痰がからんでなかなか切れないようなら、たとえば、滋陰降火湯(じいんこうかとう)など、「肺陰虚(はいいんきょ)」証を治療する漢方薬を用います。
ほかにも気管支炎を治療する漢方薬は、たくさんあります。当薬局では、漢方の専門家が一人一人の証(体質や病状)を的確に判断し、その人に最適な処方をオーダーメイドで調合しています。
予防/日常生活での注意点
気管支炎を誘発しやすいインフルエンザやかぜにかからぬよう、日頃から規則正しい生活や、適切な食事、適度な運動、じゅうぶんな睡眠を心がけ、免疫力が下がらぬよう留意しましょう。もちろん気管支に炎症をもたらしやすい喫煙を控えるのは当然です。
(こちらの記事は「薬石花房 幸福薬局」幸井俊高が執筆・監修しました。日経DIオンラインにも掲載)
*執筆・監修者紹介*
 幸井俊高 (こうい としたか)
幸井俊高 (こうい としたか)
東京大学薬学部卒業。北京中医薬大学卒業。中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。「薬石花房 幸福薬局」院長。『医師・薬剤師のための漢方のエッセンス』『漢方治療指針』(日経BP)など漢方関連書籍を25冊以上執筆・出版している。日本経済新聞社の医師・薬剤師向けサイト「日経メディカル(日経DI)」や「日経グッデイ」にて長年にわたり漢方コラムを担当・連載・執筆。中国、台湾、韓国など海外での出版も多い。17年間にわたり帝国ホテル東京内で営業したのち、ホテルの建て替えに伴い、現在は東京・銀座で営業している。
あなたに合った漢方薬が何かは、あなたの証(体質や病状)により異なります。自分に合った漢方薬を選ぶためには、正確に処方の判断ができる漢方の専門家に相談することが、もっとも安心で確実です。どうぞお気軽にご連絡ください。
関連する記事を読む
- 気管支炎(症例) (改善症例)