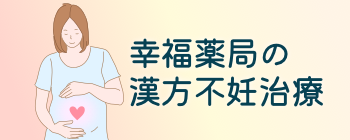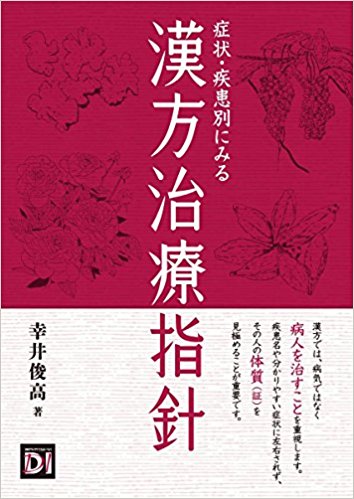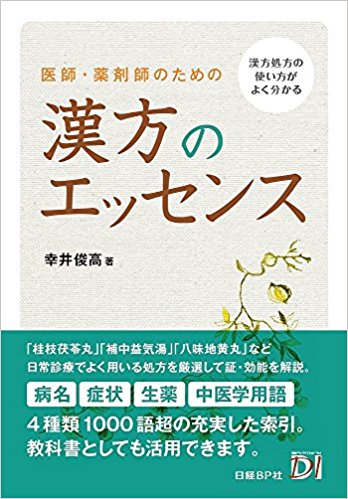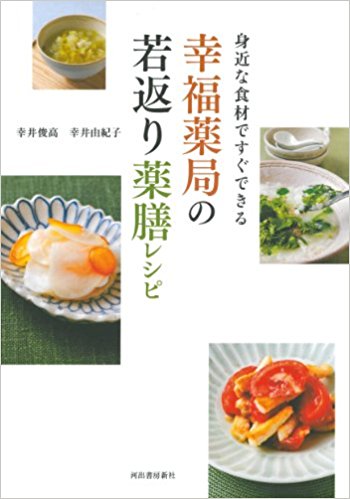慢性腎臓病(CKD)
(こちらの記事の監修:中医師 幸井俊高)
慢性腎臓病(CKD)に効く漢方薬
慢性腎臓病(CKD)の漢方治療について解説します。放置すれば腎臓の機能が低下していくので、腎臓病の予防や早期発見、重症化防止に向けて注目されています。一般の医療機関では八味地黄丸エキス顆粒などが使われることがあるようですが、だれにでも効くわけではありません。当薬局では、患者さん一人一人の体質に合わせて漢方薬を処方し、慢性腎臓病の根本治療を進めています。
*目次*
慢性腎臓病(CKD)とは
症状
原因
一般的な治療
漢方薬による治療
よく使われる漢方薬
予防/日常生活での注意点
(症例紹介ページもあります)
慢性腎臓病(CKD)とは

慢性腎臓病(CKD:Chronic Kidney Disease)は、腎臓の機能が徐々に低下していく病気の総称です。たんぱく尿など尿の異常、あるいは腎機能を表す検査値eGFR(推算糸球体濾過量)の低下、血清クレアチニン値の上昇などが長く続きます。これらは、血液を濾過して尿をつくる糸球体の機能に異常が生じていることを意味します。患者は推計で1,300万人、成人のおよそ8人に1人いると考えられています。透析患者数の増加を背景に、腎臓病の予防や早期発見、重症化防止のために注目されています。
症状
初期には自覚症状がほとんどありませんが、本人に自覚がないまま進行すると、倦怠感や、貧血、立ちくらみ、むくみ、夜間頻尿、尿の泡立ち、息切れなどの症状が表れます。尿が泡立っている場合、たんぱくが出ている可能性があります。腎機能が低下すると日中に水分をうまく排出できず、さらに夜間は頻尿となり、就寝時よりも起床時の体重が1kg以上減ることもあります。放置すれば腎不全となり、人工透析や腎移植が必要になる可能性もあります。脳卒中や心筋梗塞のリスクも高まります。壊れた糸球体は再生しないので、早期発見と早めの対策が重要です。
原因
原因としては、糖尿病、高血圧症、脂質異常症といったメタボリックシンドロームと関連が深い病気です。いずれの病気でも腎臓に負担がかかり、腎臓の機能を悪化させます。糖尿病からくる慢性腎臓病は、糖尿病腎症と呼ばれています。動脈硬化が原因となることも多く、動脈硬化により糸球体に血液が届かなくなり、糸球体が破壊されます。動脈硬化で腎臓が硬く小さくなる慢性腎臓病は、腎硬化症と呼ばれます。腎臓に炎症が起こる慢性糸球体腎炎も、慢性腎臓病のひとつです。これらの病気は、慢性腎不全となって透析を導入することになる上位を占めます。加齢による腎機能の低下もあります。
一般的な治療
慢性腎臓病(CKD)の治療には、生活習慣の改善と並行して、薬物療法によって病気の進行を遅らせたり、腎臓の機能低下による症状を緩和したりする方法や、体質的に腎臓の機能を高める方法などがあります。西洋医学では、患者さんの状態に合わせて降圧薬や利尿薬、脂質異常症改善薬、副腎皮質ステロイド薬、経口吸着薬、腎性貧血治療薬、カリウム吸着薬、リン吸着薬などが用いられます。
漢方薬による治療
漢方では、慢性腎臓病を五臓の腎(じん)と関係が深い疾患と捉えています。腎は五臓のひとつで、生命体の基本物質である精を蔵し、人の成長・発育・生殖をつかさどる基本機能のほかに、水や骨をつかさどる臓腑として、体液の代謝全般の調節や骨の形成をつかさどる機能も持ちます。体液代謝については、腎が有用な津液を上昇させて体内に供給するとともに、不要な水液を尿として膀胱に貯留して排泄します。まさに糸球体の機能そのものです。
また慢性腎臓病は、血流や体液の流れ、そして血液や体液中の老廃物とも関係の深い疾患です。これらは漢方の言葉で血瘀(けつお)、あるいは痰飲(たんいん)と呼びます。血瘀は、血の流れが鬱滞しやすい体質です。血管の微小循環障害や流動性の異常と関係があります。痰飲は、津液が水分代謝の失調などにより異常な水液と化した病理的産物です。痰飲には、体液中の老廃物なども含まれます。
したがって漢方では、五臓の腎の機能を高め、血瘀や痰飲を除去することにより、慢性腎臓病となった要因を体内から除去し、慢性腎臓病の根本的な治療や重症化の予防を進めます。初期には自覚症状がほとんどないため、主訴である慢性腎臓病以外の症状をきめ細かく聴き取り、患者さんの体質を正確に判断することが大切です。
漢方は古来、病気になる前の半健康状態を意味する未病(みびょう)を治すのが得意な医療です。病気になってしまう前に体質を改善し、病気になるのを未然に防ぎます。そういう意味では、この慢性腎臓病(CKD)には漢方治療が向いている疾患と言えます。
(症例紹介ページもあります)
よく使われる漢方薬
漢方では、患者さん一人一人の体質や病状に合わせて処方を決めます。同じ慢性腎臓病(CKD)という病名でも、体質や病状が違えば効く漢方薬も異なります。一般の医療機関では八味地黄丸エキス顆粒などが使われることがあるようですが、だれにでも効くわけではありません。以下に、慢性腎臓病に使われることの多い漢方薬を、慢性腎臓病にみられることの多い体質とともに紹介します。患者さん一人一人の体質や病状に合わせて処方を決め、治療を進めるのが漢方治療の特徴です。
- ①桂枝茯苓丸
高血圧や動脈硬化を伴う患者さんに多いのは、「血瘀(けつお)」という体質です。血行のよくない体質で、血行の悪化により腎臓に負担がかかり続けることにより、慢性腎臓病が生じます。桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)など、血液の流れを促進する漢方薬で血瘀を除去し、慢性腎臓病を治療し、重症化を予防します。
- ②大柴胡湯、小柴胡湯、柴朴湯、柴苓湯
糖尿病や脂質異常症の患者さんに多いのは、「痰飲(たんいん)」という体質です。過剰な水液が溜まりやすい体質です。過剰な水液が腎臓に負担をかけ続けると、慢性腎臓病になります。大柴胡湯(だいさいことう)、小柴胡湯(しょうさいことう)、柴朴湯(さいぼくとう)、柴苓湯(さいれいとう)など、痰飲を取り除く漢方薬を用い、慢性腎臓病の治療や重症化の予防にあたります。
- ③猪苓湯
腎臓に炎症が認められる場合にみられることが多いのは、「湿熱(しつねつ)」という体質です。湿熱は体内で過剰な湿邪と熱邪が結合したものです。湿っぽい症状や熱を帯びた症状が表れます。湿熱が糸球体などを侵して慢性的な炎症が持続すると、慢性腎臓病になります。猪苓湯(ちょうれいとう)などの湿熱を除去する漢方薬で、慢性腎臓病の治療や重症化の予防をします。
- ④八味地黄丸
頻尿、夜間頻尿、むくみなどの症状を伴う場合によくみられるのは、「腎陽虚(じんようきょ)」という体質です。腎臓の機能が低下している体質です。加齢や過労、生活の不摂生などによりこの体質になり、慢性腎臓病が生じます。八味地黄丸(はちみじおうがん)など、腎臓の機能を補う漢方薬で、慢性腎臓病の治療や重症化の予防を進めます。
- ⑤補中益気湯
倦怠感がみられるようなら、「気虚(ききょ)」という体質です。気は人体の基本的な構成成分のひとつで、生命活動や生理機能を推し進める機能に相当します。この気の作用が低下している体質です。体内の気が不足することにより腎臓の機能が低下すると、慢性腎臓病となります。補中益気湯(ほちゅうえっきとう)などの気を補う漢方薬で、慢性腎臓病を治療し、重症化を予防します。
ほかにも慢性腎臓病(CKD)にみられる体質はたくさんあります。体質が違えば薬も変わります。自分の体質を正確に判断するためには、漢方の専門家のカウンセリングを受けることが、もっとも確実で安心です。当薬局では、漢方の専門家が一人一人の体質を的確に判断し、その人に最適な処方をオーダーメイドで処方しています。
予防/日常生活での注意点
日常生活では、腎臓に負担がかからない生活習慣を心がけましょう。食事は塩分を控えめにしてください。カロリーやたんぱく質の取りすぎも要注意です。さらに、太らないよう、過食を避けて腹八分で済ましましょう。運動不足なら、運動の習慣をとりいれましょう。不規則な生活も大敵です。生活のリズムをつくり、夜ふかしは控えてください。ストレスも負担になります。たばこは厳禁です。定期的な検査も忘れないでください。
(こちらの記事は「薬石花房 幸福薬局」幸井俊高が執筆・監修しました。日経DIオンラインにも掲載)
*執筆・監修者紹介*
 幸井俊高 (こうい としたか)
幸井俊高 (こうい としたか)
東京大学薬学部卒業。北京中医薬大学卒業。中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。「薬石花房 幸福薬局」院長。『医師・薬剤師のための漢方のエッセンス』『漢方治療指針』(日経BP)など漢方関連書籍を25冊以上執筆・出版している。日本経済新聞社の医師・薬剤師向けサイト「日経メディカル(日経DI:ドラッグインフォメーション)」や「日経グッデイ」にて長年にわたり漢方コラムを担当・連載・執筆。中国、台湾、韓国など海外での出版も多い。17年間にわたり帝国ホテル東京内で営業したのち、ホテルの建て替えに伴い、現在は東京・銀座で営業している。
あなたに合った漢方薬が何かは、あなたの証(体質や病状)により異なります。自分に合った漢方薬を選ぶためには、正確に処方の判断ができる漢方の専門家に相談することが、もっとも安心で確実です。どうぞお気軽にご連絡ください。
関連する記事を読む
- 慢性腎臓病(CKD)(体験談) (改善症例)