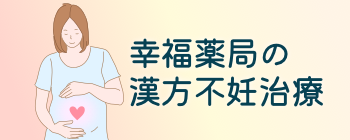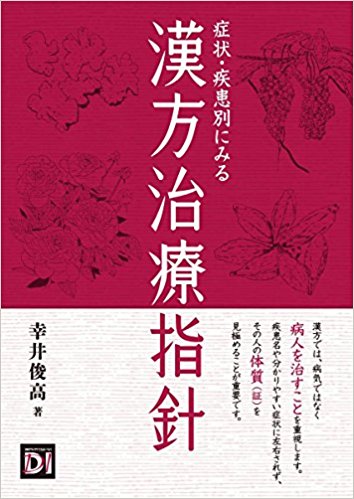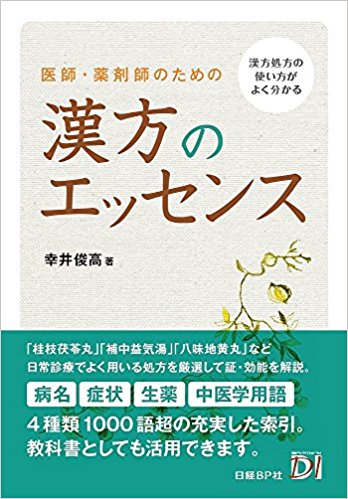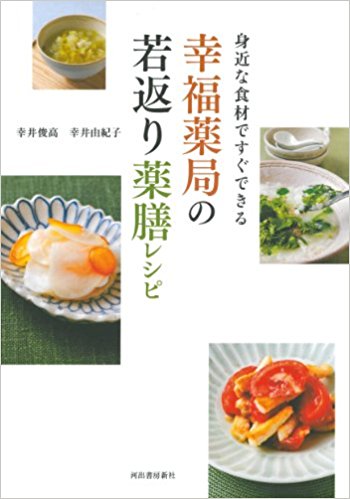卵巣嚢腫の症例
(こちらの記事の監修:中医師 幸井俊高)
◆薬石花房 幸福薬局の漢方薬で卵巣嚢腫が治った症例
こちらは症例紹介ページです。卵巣嚢腫の解説ページは こちら へどうぞ
■症例1「卵巣嚢腫があります。去年から下腹部に違和感を覚えるようになりました。最近、排卵期になると下腹部の同じ場所が痛むようになったので婦人科を受診したところ、嚢腫が5cmの大きさになっていると診断されました。手術を勧められていますが、したくありません」
症状が出始めたのは、仕事のストレスが強くなった時期と重なります。下腹部の圧迫感、月経痛があります。そのほか、頻尿気味でトイレが近い、憂鬱感、いらいらしやすい、月経前の情緒不安定や乳房の張りなどの症状があります。舌は淡紅色です。
この女性の証は、「肝鬱気滞」です。体の諸機能を調節する臓腑である肝の機能(肝気)がスムーズに働いていない体質です。ストレスの影響などで気の流れが滞ることにより、卵巣嚢腫ができやすくなります。
腹部の圧迫感、憂鬱感、いらいら、月経前の諸症状などは、この証の特徴です。ため息が多い、胸脇部が張る、などの症状がみられることもあります。
この証の場合は、漢方薬で肝気の鬱結を和らげて気の流れをスムーズにし、卵巣嚢腫ができにくい体質を作っていきます。
この女性は、漢方薬を飲み始めて2カ月目くらいから排卵期の痛みが軽減しました。半年後の検査では卵巣嚢腫が3cmと小さくなっていたので、手術はせずに経過観察することとなりました。
■症例2「病院で漿液性(しょうえきせい)嚢胞があると指摘され、経過観察中です。大きさは6cmで、これ以上大きくなるようなら手術した方がよいと言われています」
おなかを触ると塊のようなものに触れますが、特につらい自覚症状はありません。咳や痰が出ます。胃が弱く、ポリープを切除したことがあります。ときどき吐き気がします。寝付きが悪く、夢をよく見ます。舌には白い舌苔がべっとりと付着しています。
この女性の証は、「痰湿(たんしつ)」です。「痰湿凝結」ともいいます。
痰湿というのは体内にたまった過剰な水湿のことで、これが漿液性嚢胞の形成にも関わったのでしょう。胃のポリープも、恐らく痰湿によるものだったと思われます。
この体質の場合は、痰湿を取り除く漢方薬で「卵巣嚢腫ができやすい体質」を改善し、卵巣嚢腫の治療に当たります。
漢方薬を飲み続けてもらった結果、卵巣嚢腫は9カ月後の検査では3cmにまで小さくなりました。
■症例3「排卵期や月経前に腹痛があり、それが少しずつ強くなってきているので婦人科を受診したところ、卵巣嚢腫が見つかりました。粘液性嚢胞とのことです」
むくみやすく、特に下半身がむくみます。手足がだるく感じます。色の付いた帯下(たいげ、おりもの)が気になります。慢性的な便秘症です。舌は紅色で、黄色い舌苔がべっとりと付着しています。
この女性の証も、「痰湿(たんしつ)」です。痰湿が粘液性嚢胞を形成したと思われます。
むくみやすい、手足がだるい、べっとりとした舌苔などは、この証の特徴です。めまい、動悸などの症状がみられることもあります。
この女性は漢方薬を服用した結果、腹痛は徐々に治まり、卵巣嚢腫も経過観察で済んでいます。便秘も解消されました。
(こちらの記事は「薬石花房 幸福薬局」幸井俊高が執筆・監修しました。日経DIオンラインにも掲載)
*執筆・監修者紹介*
 幸井俊高 (こうい としたか)
幸井俊高 (こうい としたか)
東京大学薬学部卒業。北京中医薬大学卒業。中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。「薬石花房 幸福薬局」院長。『医師・薬剤師のための漢方のエッセンス』『漢方治療指針』(日経BP)など漢方関連書籍を25冊以上執筆・出版している。日本経済新聞社の医師・薬剤師向けサイト「日経メディカル(日経DI)」や「日経グッデイ」にて長年にわたり漢方コラムを担当・連載・執筆。中国、台湾、韓国など海外での出版も多い。17年間にわたり帝国ホテル東京内で営業したのち、ホテルの建て替えに伴い、現在は東京・銀座で営業している。
あなたに合った漢方薬が何かは、あなたの証(体質や病状)により異なります。自分に合った漢方薬を選ぶためには、正確に処方の判断ができる漢方の専門家に相談することが、もっとも安心で確実です。どうぞお気軽にご連絡ください。
関連する記事を読む
- 卵巣嚢腫 (病気・症状)