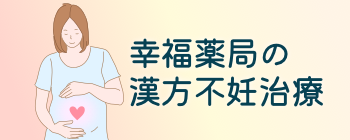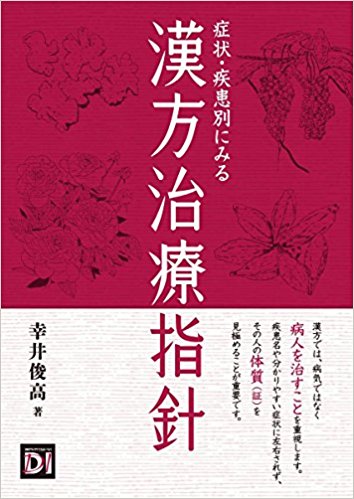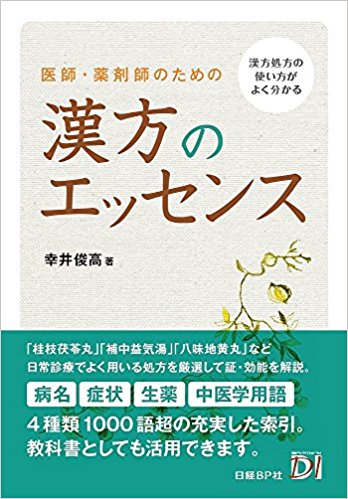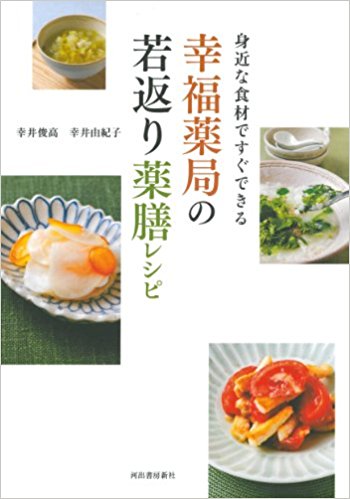変形性膝関節症
変形性膝関節症に効く漢方薬
(こちらの記事の監修:中医師 幸井俊高)
変形性膝関節症の漢方治療について解説します。一般には消炎鎮痛薬や湿布薬、ヒアルロン酸の注射などが行われますが、再発したり完治しなかったりすることも多い病気です。漢方薬としては防已黄耆湯などが使われることがあるようですが、これも体質が合わないと効きません。当薬局では、患者さん一人一人の体質に合わせて漢方薬を処方し、変形性膝関節症の根本治療を進めています。
*目次*
変形性膝関節症とは
症状
原因
一般的な治療
漢方薬による治療
よく使われる漢方薬
予防/日常生活での注意点
(症例紹介ページもあります)
変形性膝関節症とは

変形性膝関節症(へんけいせいしつかんせつしょう)は、膝関節のクッションの役割を果たしている関節軟骨がすり減り、関節内に炎症が起きたり膝関節が変形したりする疾患です。男性より女性に多くみられ、高齢になるほど罹患率が高くなり、80代では女性の8割、男性の5割に発病するといわれています。
症状
よくみられる症状には、歩くときに痛みを感じる、とくに歩き始めや立ち上がったときなどの動作開始時が痛い、正座をすると膝が痛い、階段の登り降りがつらい、などの膝の痛みや、関節の腫れなどあります。膝関節に水がたまることもあります。また、外反母趾(がいはんぼし)や巻き爪が起こりやすくなります。適切な治療や予防を怠ると、関節や骨の変形が進み、治療が難しくなります。
原因
原因としては、運動不足などによる筋力の低下や、習慣的な長時間の立ち仕事、体重の増加による膝への負担の増加、O(オー)脚(内反膝:ないはんしつ)などがあります。また、猫背、いつも脚を組む、横座りなどの悪い姿勢でいると、骨盤や膝関節がゆがみやすくなります。さらに加齢に伴い、膝の関節が脆弱になり、まわりの筋肉が衰え、膝関節や骨盤への負担が増すと、膝関節や骨盤がゆがみやすくなり、変形性膝関節症が引き起こされやすくなります。偏った食生活でビタミンDの摂取量が不足しても骨が曲がりやすくなります。
一般的な治療
治療法には、痛みを抑える対症療法や、筋肉や関節可動域を改善する運動器リハビリテーション、さらに変形性膝関節症になりやすい体質そのものや痛みの根本原因を改善していく原因療法などがあります。西洋医学では、非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)などの内服薬や外用薬(湿布薬)、ヒアルロン酸の注射などによる対症療法が行われます。改善されない場合は手術が検討されます。
漢方薬による治療
漢方では、変形性膝関節症になりやすい体質そのものや痛みの根本原因を改善していく原因療法により、変形性膝関節症の治療を進めます。
漢方では、痛みは気・血(けつ)・津液(しんえき)など人体の構成成分の「流れ」や「量」と深い関係にあると捉えています。気は生命エネルギーに近い概念、血は全身を滋養する血液や栄養、津液は体内の水液を指します。
流れについては、中医学に「不通則痛(ふつうそくつう)」という言葉があります。「通じざれば、すなわち痛む」と読みます。体内での気・血・津液の流れがスムーズでないと痛みが生じる、という意味です。
量については、「不栄則痛(ふえいそくつう)」という原則があります。「栄えざれば、すなわち痛む」と読みます。人体にとって必要な気・血・津液が不足すると痛みが生じる、という意味です。エネルギーや栄養、潤いがじゅうぶん供給されないと、その部分が正常に機能できず、痛みが生じます。
そして関節や筋肉にしびれや痛み、運動障害などが生じる病態を、漢方では痺証(ひしょう)と呼んでいます。人体にくまなく分布している経絡が病邪によって塞がれて閉じ、気・血・津液の流れが妨げられると、筋肉や関節に疼痛やしびれが表れます。経絡は気・血・津液が運行する通路です。変形性膝関節症は、痺証のひとつです。
痺証は気・血・津液の流れの停滞による証ですが(不通則痛)、ベースには気・血・津液が不足して経絡が空虚になっている状態があります(不栄則痛)。したがって漢方では、気・血・津液の流れをととのえ、病邪を除去し、痺証を治療することにより、変形性膝関節症の治療を進めます。
(症例紹介ページもあります)
よく使われる漢方薬
漢方では、患者さん一人一人の体質や病状に合わせて処方を決めます。同じ変形性膝関節症という病名でも、体質や病状が違えば効く漢方薬も異なります。一般には防已黄耆湯などが使われることがあるようですが、だれにでも効くわけではありません。以下に、変形性膝関節症に使われることの多い漢方薬を、みられることの多い体質とともに紹介します。患者さん一人一人の体質や病状に合わせて処方を決め、治療を進めるのが漢方治療の特徴です。
- ①薏苡仁湯、麻杏薏甘湯、防已黄耆湯
膝が重だるく、痛みやしびれがいつも同じ部位(固定性)で生じているようなら、漢方でいう「着痺(ちゃくひ)」という体質です。湿邪による痺証です。湿邪とは、津液が停滞して生じる病邪です。湿邪が重く停滞し、固定性の重だるい痛みやしびれが生じます(これらは湿邪の特徴です)。関節に水がたまることもあります。朝起きたときなど動き始めるときに痛むのも特徴です。着痺のことを湿痺(しっぴ)ともいいます。薏苡仁湯(よくいにんとう)、麻杏薏甘湯(まきょうよくかんとう)、防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)など、湿邪を除去する漢方薬で、変形性膝関節症を治します。
- ②桂枝加朮附湯
強い固定性の痛みがあり、とくに冷えた環境などで痛みが悪化するなら、「痛痺(つうひ)」という体質です。寒邪が侵入することにより生じる痺証です。寒邪とは、強い冷えが原因となっている場合の病邪です。寒邪は気血を凝滞させやすいため、固定性の激しい疼痛が生じます。痛みは、冷えると強くなり、温めると楽になります(これらは寒邪の特徴です)。痛痺のことを寒痺(かんぴ)とも呼びます。桂枝加朮附湯(けいしかじゅつぶとう)など、寒邪を除去する漢方薬で、変形性膝関節症の治療を進めます。
- ③越婢加朮湯、白虎湯
患部に熱感、発赤、腫脹などがあるようなら、「熱痺(ねっぴ)」という体質です。熱邪による痺証です。熱邪とは、熱が原因となって病気となっている場合の病邪です。熱邪が強いため、発赤や熱感などの熱証があらわれます。症状は冷やすと軽減します(これらは熱邪の特徴です)。越婢加朮湯(えっぴかじゅつとう)や白虎湯(びゃっことう)など、熱邪を除去する漢方薬で、変形性膝関節症を治療します。
- ④防風湯
痛みが移動性で、あちらこちらと移動しやすい場合(遊走性)は、「行痺(こうひ)」という体質です。風邪(ふうじゃ)による痺証です。風邪とは、風のように移動しやすい病邪です。風邪が経絡を侵すため、関節の疼痛、しびれ、運動障害などの症状は多発性で、その部位は遊走し、固定しません(これらは風邪の特徴です)。行痺のことを風痺(ふうひ)とも呼びます。防風湯(ぼうふうとう)など、風邪を除去する漢方薬で、変形性膝関節症の治療を進めます。
- ⑤牛車腎気丸、八味地黄丸
加齢に伴い生じた膝の痛みなら、「腎陽虚(じんようきょ)」という体質です。五臓の腎(じん)の機能が低下している体質です。腎は五臓のひとつで、「骨をつかさどる」臓腑として、骨の形成に深く関与します。したがって腎の機能が衰えると、骨や関節に異常が生じやすくなります。牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)や八味地黄丸(はちみじおうがん)など、腎の機能を補う漢方薬で、変形性膝関節症の治療を進めます。
- ⑥四物湯
しびれ感が強いようなら、「血虚(けっきょ)」という体質です。人体の構成成分のひとつである血の滋養作用が低下している状態です。血の不足により組織がじゅうぶんに滋養されないと、その部分が正常に機能できず、痛みやしびれが生じます。四物湯(しもつとう)など、血を補う漢方薬で、変形性膝関節症を治療します。
ほかにも変形性膝関節症にみられる体質はたくさんあります。体質が違えば薬も変わります。自分の体質を正確に判断するためには、漢方の専門家の診察(カウンセリング)を受けることが、もっとも確実で安心です。当薬局では、漢方の専門家が一人一人の体質を的確に判断し、その人に最適な処方をオーダーメイドで処方しています。
予防/日常生活での注意点
日常生活では、体重が増えすぎると膝への負担が大きくなるので、体重増加に気をつけましょう。筋肉が少ないと関節への負担が増えるので、スクワットなど下半身の筋力トレーニングも役立ちます。膝の可動域を維持するためストレッチも効果的です。デスクワークが続くと猫背になりやすいので、1時間に1度程度は立ち上がり、少し歩きましょう。食べ物では、ビタミンDが不足すると骨が曲がりやすくなるので、ビタミンDを多く含む魚類や乳製品をとりましょう。日光を浴びないのも骨が弱くなる原因です。関節や骨が変形してしまうと治療が難しいので、早いうちから予防しておきましょう。
(こちらの記事は「薬石花房 幸福薬局」幸井俊高が執筆・監修しました。日経DIオンラインにも掲載)
*執筆・監修者紹介*
 幸井俊高 (こうい としたか)
幸井俊高 (こうい としたか)
東京大学薬学部卒業。北京中医薬大学卒業。中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。「薬石花房 幸福薬局」院長。『医師・薬剤師のための漢方のエッセンス』『漢方治療指針』(日経BP)など漢方関連書籍を25冊以上執筆・出版している。日本経済新聞社の医師・薬剤師向けサイト「日経メディカル(日経DI:ドラッグインフォメーション)」や「日経グッデイ」にて長年にわたり漢方コラムを担当・連載・執筆。中国、台湾、韓国など海外での出版も多い。17年間にわたり帝国ホテル東京内で営業したのち、ホテルの建て替えに伴い、現在は東京・銀座で営業している。
あなたに合った漢方薬が何かは、あなたの証(体質や病状)により異なります。自分に合った漢方薬を選ぶためには、正確に処方の判断ができる漢方の専門家に相談することが、もっとも安心で確実です。どうぞお気軽にご連絡ください。
関連する記事を読む
- 変形性膝関節症(体験談) (改善症例)
- 検査で異常ない膝の痛み、漢方だから治せた (ストーリー)
- 手足のしびれ ・ 神経痛 (病気・症状)