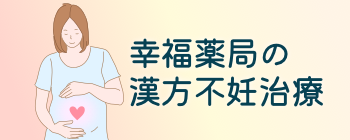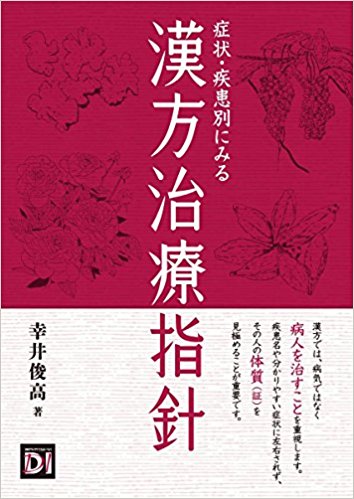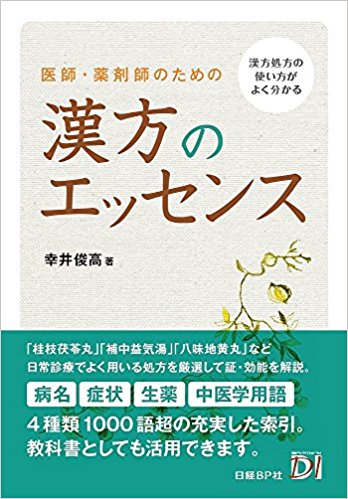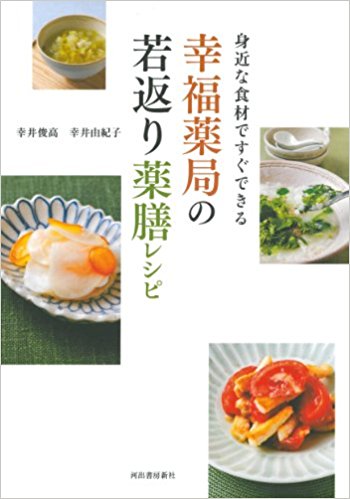慢性疲労症候群(ME/CFS)
(こちらの記事の監修:中医師 幸井俊高)
慢性疲労症候群(ME/CFS)に効く漢方薬
慢性疲労症候群(ME/CFS)の漢方治療について解説します。一般にはビタミン剤などによる対症療法が行われますが、改善しなかったり再発したり完治しなかったりすることの多い病気です。漢方薬としては補中益気湯などが使われることがあるようですが、これも体質が合わないと効きません。当薬局では、患者さん一人一人の体質に合わせて漢方薬を処方し、慢性疲労症候群(ME/CFS)の根本治療を進めています。
*目次*
慢性疲労症候群(ME/CFS)とは
症状
原因
一般的な治療
漢方薬による治療
よく使われる漢方薬
予防/日常生活での注意点
(症例紹介ページもあります)
慢性疲労症候群(ME/CFS)とは

慢性疲労症候群(ME/CFS)は、身体と精神の両方に激しい疲労感が長期間にわたり続く疾患です。疲労感は強く、朝起きたときからひどい疲労を感じ、日常生活に支障をきたすほどの疲労感です。じゅうぶんな休養をとっても回復しません。一般の慢性疲労と混同されるのを避けるため、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)と称されます。
症状
強い疲労感のほかにも、さまざまな症状が表れます。微熱、喉の痛み、頭痛、思考力の低下、抑うつ状態、睡眠障害(不眠、過眠)、筋力の低下、筋肉痛、関節痛、光や音への過敏性、頚部などのリンパ節がはれる、などです。20〜50歳台に発症することが多く、男性より女性に多くみられるようです。
原因
原因については、ストレスや免疫異常、ウイルス感染などが考えられていますが、今のところ明らかにはわかっていないようです。誰もが日常生活で経験する疲労や慢性疲労とは違い、免疫系や神経系、内分泌系などが関与する疾患だと考えられています。神経伝達物質や脳内血流量の低下も関係しているといわれています。
一般的な治療
西洋医学では、ビタミン剤や、抗うつ薬、鎮痛薬などを用いた薬物療法による対症療法が行われています。漢方エキス剤が対症療法的に使われることもあります。
漢方薬による治療
漢方では、慢性疲労症候群(ME/CFS)を、五臓の腎(じん)、心(しん)、肝(かん)の機能失調と関係が深い疾患と捉えています。
腎は五臓のひとつで、生きるために必要な基本物質を貯蔵し、人の成長・発育・生殖をつかさどる臓腑です。この腎の機能が低下すると疲労が慢性化し、慢性疲労症候群になります。
心も五臓のひとつで、人間の判断や思考などの精神活動をつかさどる臓腑です。この心がじゅうぶん養われていないと、精神活動が弱まり、慢性疲労症候群が生じます。
肝も五臓のひとつで、体の諸機能を調節し、情緒を安定させる臓腑です。この肝の機能が失調すると、自律神経系が不安定となり、慢性疲労症候群が発生します。
したがって漢方では、五臓の腎、心、肝の機能を正常化させることなどにより、慢性疲労症候群の治療を進めます。
(症例紹介ページもあります)
よく使われる漢方薬
漢方では、患者さん一人一人の体質や病状に合わせて処方を決めます。同じ慢性疲労症候群(ME/CFS)という病名でも、体質や病状が違えば効く漢方薬も異なります。一般には補中益気湯などが使われることがあるようですが、だれにでも効くわけではありません。以下に、慢性疲労症候群に使われることの多い漢方薬を、みられることの多い体質とともに紹介します。患者さん一人一人の体質や病状に合わせて処方を決め、治療を進めるのが漢方治療の特徴です。
- ①六味地黄丸
強い疲労感とともに、思考力の低下、微熱、からだの熱感(とくに午後)、寝汗などの症状がみられるようなら、漢方でいう「腎陰虚(じんいんきょ)」という体質です。生きるために必要なエネルギーや栄養が不足している状態です。免疫系や内分泌系に異常が生じて腎の機能が低下するとこの体質になり、慢性疲労症候群となります。この体質の場合は、六味地黄丸(ろくみじおうがん)など、腎を補う漢方薬を用いて慢性疲労症候群の治療をします。
- ②帰脾湯
強い疲労感とともに、寝つきがわるい、よく目が覚める、夢をよく見る、朝早く目がさめる、などの睡眠障害がみられるようなら、「心血虚(しんけっきょ)」という体質です。判断や思考をつかさどる五臓の心の機能がじゅうぶん養われていない体質です。過度の心労、思い悩み過ぎ、過労の持続などにより心に負担がかかり続けるとこの体質になり、慢性疲労症候群が生じます。帰脾湯(きひとう)などの漢方薬で五臓の心を養うことにより、慢性疲労症候群の治療をしていきます。
- ③十全大補湯
強い疲労感とともに、脱力感、動きたがらない、無気力、動作緩慢、しゃべりたがらない、などの症状がみられるようなら、「気血両虚(きけつりょうきょ)」という体質です。生命エネルギーを意味する「気」と、血液や栄養を意味する「血(けつ)」の両方が不足している状態です。気血の欠乏により脳内血流量の低下などが生じると、慢性疲労症候群となります。十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)などを用い、不足している気血を漢方薬で補うことにより、慢性疲労症候群の治療をします。
- ④杞菊地黄丸
強い疲労感とともに、目が疲れやすい、筋肉の引きつり、筋肉痛、女性の場合は過少月経(月経量が少ない)や稀発月経(月経が遅れる)を伴う場合は、「肝陰虚(かんいんきょ)」という体質です。体の諸機能を調節して情緒を安定させる五臓の肝(かん)がじゅうぶんに養われていない状態です。ストレスや緊張の持続などの影響を受けるとこの状態になり、慢性疲労症候群が生じます。杞菊地黄丸(こぎくじおうがん)など、肝を補う漢方薬で、慢性疲労症候群を治療します。
- ⑤小柴胡湯、柴胡加竜骨牡蛎湯
強い疲労感とともに、微熱、頭痛、喉の痛み、頚部などのリンパ節がはれる、などの症状がみられる場合は、「肝火(かんか)」という体質です。五臓の肝の機能が精神的なストレスなどの影響によりスムーズに働かなくなって亢進すると、この体質になります。自律神経系の亢進が続くと強い疲労感が生じ、慢性疲労症候群となります。小柴胡湯(しょうさいことう)、柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)などの漢方薬で肝の機能をととのえることにより、慢性疲労症候群を治療していきます。
- ⑥補中益気湯
強い疲労感とともに、手足がだるい、筋力の低下、食べると眠くなる、などの症状もみられる場合は、「中気下陥(ちゅうきげかん)」という体質です。気が足りなくて臓器を定位置にとどめる力が弱く、筋肉の緊張も弱まって何もかもが垂れ下がっているような状態です。気がじゅうぶんに補われるまで疲労感が長く続く、慢性疲労症候群の状態です。この体質には、補中益気湯(ほちゅうえっきとう)など、気を補う漢方薬を用いて慢性疲労症候群を治療します。
ほかにも慢性疲労症候群(ME/CFS)にみられる体質はたくさんあります。体質が違えば薬も変わります。自分の体質を正確に判断するためには、漢方の専門家の診察(カウンセリング)を受けることが、もっとも確実で安心です。当薬局では、漢方の専門家が一人一人の体質を的確に判断し、その人に最適な処方をオーダーメイドで処方しています。
予防/日常生活での注意点
日常生活では、無理をせず、じゅうぶんな休息をとるようにしましょう。規則正しい生活と、質の高い睡眠を心がけましょう。食事は旬の食材を中心にバランスよくとりましょう。リラックスできる環境をつくり、ウォーキングなどの軽い運動をするなど、ストレスをためない工夫も大切です。
(こちらの記事は「薬石花房 幸福薬局」幸井俊高が執筆・監修しました。日経DIオンラインにも掲載)
*執筆・監修者紹介*
 幸井俊高 (こうい としたか)
幸井俊高 (こうい としたか)
東京大学薬学部卒業。北京中医薬大学卒業。中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。「薬石花房 幸福薬局」院長。『医師・薬剤師のための漢方のエッセンス』『漢方治療指針』(日経BP)など漢方関連書籍を25冊以上執筆・出版している。日本経済新聞社の医師・薬剤師向けサイト「日経メディカル(日経DI:ドラッグインフォメーション)」や「日経グッデイ」にて長年にわたり漢方コラムを担当・連載・執筆。中国、台湾、韓国など海外での出版も多い。17年間にわたり帝国ホテル東京内で営業したのち、ホテルの建て替えに伴い、現在は東京・銀座で営業している。
あなたに合った漢方薬が何かは、あなたの証(体質や病状)により異なります。自分に合った漢方薬を選ぶためには、正確に処方の判断ができる漢方の専門家に相談することが、もっとも安心で確実です。どうぞお気軽にご連絡ください。
関連する記事を読む
- 慢性疲労症候群(ME/CFS)(体験談) (改善症例)
- 漢方で「やる気」復活、肌の調子もUp! (ストーリー)
- 疲労倦怠感、やる気・気力の減退 (病気・症状)