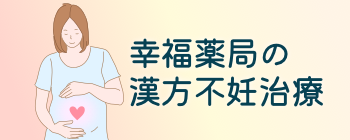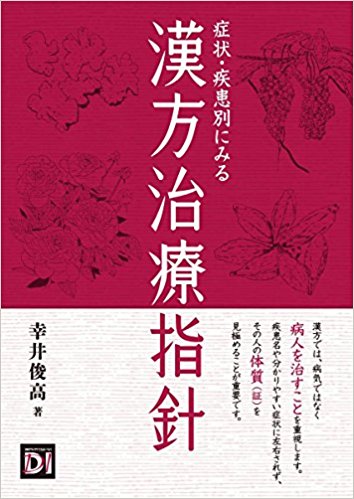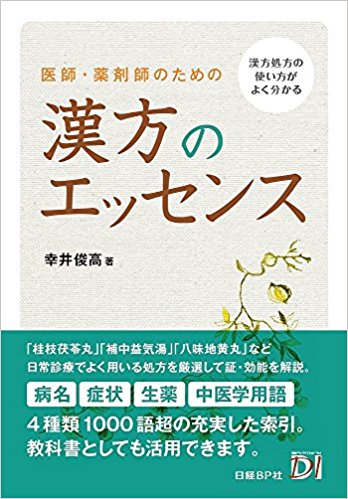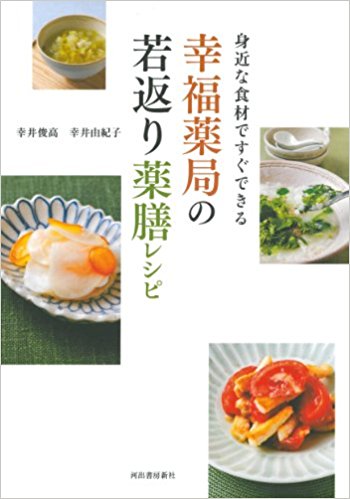不眠症(中途覚醒)
不眠症(中途覚醒)に効く漢方薬
(こちらの記事の監修:中医師 幸井俊高)
不眠症の一種である中途覚醒の漢方治療について解説します。一般には睡眠薬や抗不安薬が処方されますが、なかなか薬なしで朝まで熟睡できるようにはならないことも多い病気です。漢方薬としては酸棗仁湯や柴胡加竜骨牡蛎湯が使われることがあるようですが、これも体質が合わないと効きません。当薬局では、患者さん一人一人の体質に合わせて漢方薬を処方し、中途覚醒の根本治療を進めています。
*目次*
不眠症(中途覚醒)とは
症状
原因
一般的な治療
漢方薬による治療
よく使われる漢方薬
予防/日常生活での注意点
(症例紹介ページもあります)
不眠症(中途覚醒)とは

中途覚醒は、寝ている間に何度か目が覚める、不眠症の一種です。加齢に伴い増加する傾向にあります。なお不眠症には以下の4タイプがあります。
入眠障害 眠るまでに時間がかかる
中途覚醒 睡眠の途中で目が覚めてしまう
早朝覚醒 必要以上に早く目が覚めてしまう
熟眠障害 眠った満足感がない
症状
よくみられる症状は、深夜に何度も目が覚める、物音や気配を敏感に感じて目が覚めやすい、中途覚醒のあと寝つきにくい、不安感が強くて深夜に目が覚める、寝つきは問題ないが睡眠の途中で目が覚めやすい、などです。睡眠がじゅうぶん足りていないため、日中に慢性的な眠気に襲われることもあります。
原因
原因としては、精神的なストレス、不規則な生活、過労、加齢、運動不足、過度の飲酒などがあります。睡眠時無呼吸症候群や自律神経失調症、うつ病、レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)などの病気が背景にある場合や、更年期などのホルモンバランスの乱れが関係している場合もあります。
一般的な治療
治療には、薬物療法によって脳の活動を抑制させて眠気を誘う対症療法や、心身の自然なリズムを取り戻すことにより自然な眠りへと導く方法などがあります。西洋医学では、おもに薬物療法が行われます。薬の力で脳の活動を抑制させ、眠気を誘います。ベンゾジアゼピン受容体作動薬などの睡眠薬をはじめ、抗不安薬、抗うつ薬、精神安定剤などが使われます。
漢方薬による治療
漢方では、昼と夜が日々繰り返されるという一日のリズムに心身を合わせていくことにより、中途覚醒の治療をします。
地球上には太古より昼と夜がありました。人類が誕生したときにも、すでに昼と夜という一日のリズムがありました。したがって人の心身は、昼と夜が毎日繰り返すという地球のリズムに合わせてできています。昼は陽、夜は陰に属しますので、昼は陽気が盛んになって意識や情緒が清らかで活発ではっきりし、夜は陰気が盛んになって意識や情緒が安らかに静まり、眠くなる、というのが自然なサイクルです。体内での陰陽のバランスがととのっていれば、夜が更けると自然に眠くなり、ぐっすりと眠れます。
しかし、なんらかの理由でこの陰陽バランスが乱れると、夜遅くなっても意識や情緒が興奮状態のままで眠れなくなります。ぐっすり眠るべき時間帯に眠れるか眠れないかの点で大事なのは、意識や情緒の興奮や鎮静が昼夜という自然の流れとともにあるかどうかです。したがって人体内の陰陽を調和させることが、中途覚醒の漢方治療の基本です。
不眠症(中途覚醒)において、とくに重要なのは、五臓六腑の肝(かん)、心(しん)、脾(ひ)や、痰飲(たんいん)、熱邪です。肝、心、脾は五臓のひとつで、それぞれ精神情緒や自律神経系、意識や思惟など高次の精神活動、消化吸収や代謝と関係が深い臓腑です。痰飲は体内の異常な水液、熱邪は熱により生じる症状を引き起こす病邪です。
これらのうち、とくに中途覚醒と関係が深いのは五臓の「心(しん)」です。心は、人間の意識や判断など人間らしい高次の精神活動(「神志(しんし)といいます)をつかさどります。この心において陰陽が調和していれば、夜になるにつれて意識が穏やかに安定して静まり、眠りが深くなり、中途覚醒が減ります。したがって漢方では、おもに五臓の心の陰陽バランスを調和させることにより、中途覚醒の治療を進めます。
(症例紹介ページもあります)
よく使われる漢方薬
漢方では、患者さん一人一人の体質や病状に合わせて処方を決めます。同じ不眠症(中途覚醒)という病名でも、体質や病状が違えば効く漢方薬も異なります。一般には酸棗仁湯や柴胡加竜骨牡蛎湯が使われることがあるようですが、だれにでも効くわけではありません。以下に、中途覚醒に使われることの多い漢方薬を、みられることの多い体質とともに紹介します。患者さん一人一人の体質や病状に合わせて処方を決め、治療を進めるのが漢方治療の特徴です。
- ①桂枝加竜骨牡蛎湯
中途覚醒とともに、夜などに動悸が生じやすいようなら、漢方でいう「心気虚(しんききょ)」という体質です。考えすぎや心労の積み重ねにより、五臓の心の機能が低下すると、この体質になります。心の機能が弱まると睡眠が浅くなり、中途覚醒が起こります。この体質の場合は、桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)などの漢方薬で、心の機能を補うことにより、中途覚醒を治療します。
- ②酸棗仁湯、甘麦大棗湯
毎日のように夢を見て眠りが浅いようなら、漢方でいう「心血虚(しんけっきょ)」という体質です。五臓の心がじゅうぶん養いきれていない体質です。思い悩み過ぎや過労が続くことにより心に負担がかかり続けると、この体質になります。加齢によりこの体質になる場合もあります。五臓の心がじゅうぶん潤わないことにより、中途覚醒が起こります。酸棗仁湯(さんそうにんとう)や甘麦大棗湯(かんばくたいそうとう)などの漢方薬で心を潤し、中途覚醒の治療をします。
- ③天王補心丹
驚きやすい、些細なことで緊張しやすい、というタイプの中途覚醒なら、「心陰虚(しんいんきょ)」という体質です。こちらも五臓の心がじゅうぶん養われていない体質ですが、さほど夢ばかり見て眠りが浅いのとは異なる体質です。やはり過度の心労や過労が続くことにより、この体質になると、中途覚醒が生じます。天王補心丹(てんのうほしんたん)などの漢方薬で心の潤いを補い、神志を安定させ、中途覚醒の治療をします。
- ④帰脾湯、加味帰脾湯
不安感、疲れやすい、などの症状がみられる場合は、「心脾両虚(しんぴりょうきょ)」という体質です。五臓の心の潤いが不足していると同時に、五臓の脾がつかさどる胃腸機能が低下している体質です。五臓の心と脾は密接な関係にあり、脾の胃腸機能が弱いと栄養が不足して心が養われませんし、心が疲れると消化吸収機能が失調します。そしてこの体質になって精神活動が不安定になると、中途覚醒になります。帰脾湯(きひとう)や加味帰脾湯(かみきひとう)など、胃腸機能を高めつつ心を潤す漢方薬で、中途覚醒を治療します。
- ⑤黄連阿膠湯
焦燥感が強く、寝汗をかくようなら、漢方でいう「心腎不交(しんじんふこう)」という体質です。腎も心と同じく五臓のひとつで、全身を養い潤す働きがあります。健康な状態では、腎が心を潤して安定させ、心が腎を温めて腎の機能を安定させています。この均衡が崩れているのが、この体質です。精神的なストレスや緊張、過労などにより、この体質になります。心の機能が失調することにより、中途覚醒になります。黄連阿膠湯(おうれんあきょうとう)などの漢方薬で五臓の心と腎の関係を修復することにより、中途覚醒の治療を進めます。
- ⑥柴胡加竜骨牡蛎湯
怖い夢を見て目覚めることが多いようなら、漢方でいう「心胆気虚(しんたんききょ)」という体質です。胆は六腑のひとつで、ものごとの決断をつかさどる働きがあります。この六腑の胆と、五臓の心の両方の機能が低下しているのが、この体質です。この体質になると、判断力や決断力が弱まり、落ち着きがなくなり、中途覚醒するようになります。柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)などの漢方薬で、心と胆の機能を安定させていくことで、中途覚醒の治療を進めます。
ほかにも中途覚醒にみられる体質はたくさんあります。体質が違えば薬も変わります。自分の体質を正確に判断するためには、漢方の専門家の診察(カウンセリング)を受けることが、もっとも確実で安心です。当薬局では、漢方の専門家が一人一人の体質を的確に判断し、その人に最適な処方をオーダーメイドで処方しています。
予防/日常生活での注意点
日常生活では、規則正しい生活を心がけましょう。毎日およそ同じ時間に起き、同じ時間に食事をすることで、体内時計のリズムが安定し、一日の中でのオンとオフがはっきりしてきます。生活のリズムが乱れると、オンとオフが曖昧になり、夜によく眠れず、昼間にぼんやりするようになります。食事はゆっくり楽しんでいただきましょう。ぬるめのお風呂や、アロマセラピー、心を落ち着かせる音楽などにも、体内時計を休息の時間に導く力があるようです。運動不足やストレスは、深い睡眠の大敵です。散歩やストレッチの習慣を取り入れましょう。深酒や、水分、カフェインのとりすぎにも注意したほうがいいようです。起床後に太陽の光を浴びると体内時計のリズムが整うともいわれています。
(こちらの記事は「薬石花房 幸福薬局」幸井俊高が執筆・監修しました。日経DIオンラインにも掲載)
*執筆・監修者紹介*
 幸井俊高 (こうい としたか)
幸井俊高 (こうい としたか)
東京大学薬学部卒業。北京中医薬大学卒業。中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。「薬石花房 幸福薬局」院長。『医師・薬剤師のための漢方のエッセンス』『漢方治療指針』(日経BP)など漢方関連書籍を25冊以上執筆・出版している。日本経済新聞社の医師・薬剤師向けサイト「日経メディカル(日経DI:ドラッグインフォメーション)」や「日経グッデイ」にて長年にわたり漢方コラムを担当・連載・執筆。中国、台湾、韓国など海外での出版も多い。17年間にわたり帝国ホテル東京内で営業したのち、ホテルの建て替えに伴い、現在は東京・銀座で営業している。
あなたに合った漢方薬が何かは、あなたの証(体質や病状)により異なります。自分に合った漢方薬を選ぶためには、正確に処方の判断ができる漢方の専門家に相談することが、もっとも安心で確実です。どうぞお気軽にご連絡ください。
関連する記事を読む
- 不眠症(中途覚醒)(体験談) (改善症例)
- 不眠症の症例 (改善症例)
- 不眠・漢方で考え方も変化、自然な眠りへ (ストーリー)
- 失恋からの不眠→自然な眠りを取り戻すまで (ストーリー)
- 良質な睡眠は美容と健康のカギ (ストーリー)
- 不眠症 (病気・症状)