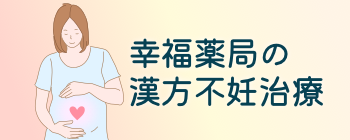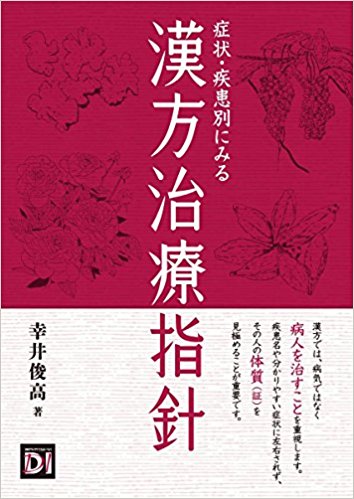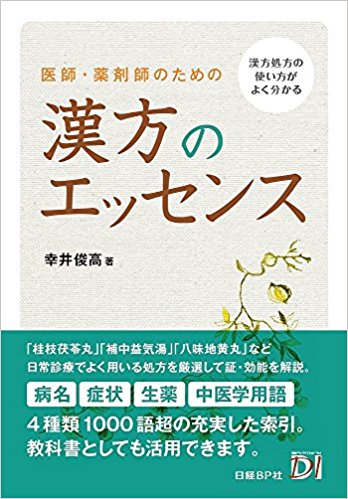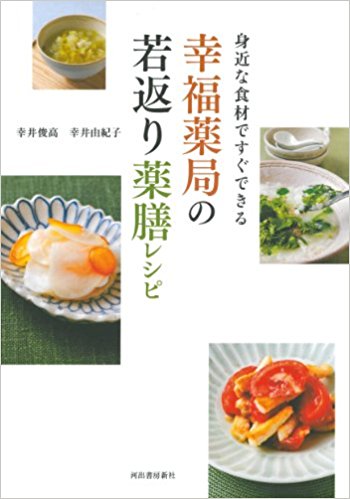多汗症・体臭・加齢臭
(こちらの記事の監修:中医師 幸井俊高)
多汗症・体臭・加齢臭に効く漢方薬
多汗症・体臭・加齢臭の漢方治療について解説します。一般には外用薬や注射などの対症療法が行われますが、再発したり完治しなかったり副作用が強かったりすることが多いのが実情です。漢方薬としては防已黄耆湯などが使われることがあるようですが、これも体質が合わないと効きません。当薬局では、患者さん一人一人の体質に合わせて漢方薬を処方し、多汗症・体臭・加齢臭の根本治療を進めています。
*目次*
多汗症・体臭・加齢臭とは
症状
原因
一般的な治療
漢方薬による治療
よく使われる漢方薬
予防/日常生活での注意点
(症例紹介ページもあります)
多汗症・体臭・加齢臭とは

多汗症は、体温調節などに必要な量を超えて、汗の分泌が異常に増えてしまう疾患です。全身から汗をかく全身性多汗症と、手のひら、足の裏、脇の下、顏など局所的に汗が増える局所性多汗症があります。
汗や皮脂が皮膚表面に常在する細菌により分解されると、体臭が生じます。とくに年齢を重ねるにつれて強くなる体臭が、加齢臭です。
症状
多汗症の症状は、日常生活に支障をきたすほどの過剰な発汗です。ひどい場合は、手のひらや顔からしたたり落ちるほどの発汗がみられます。仕事や勉学への影響も大きく、また対人関係に支障をきたすこともあり、患者さんのQOL(生活の質)が悪化します。
体臭は本来だれにでもあるものですが、体臭や加齢臭が強くなると、ときに不快な臭いとなり、周囲の人に気づかれないか、あるいは嫌われやしないか、などという気持ちにもなります。
原因
多汗症の原因としては、内分泌異常、温熱性発汗、感染症などがあります。肥満や糖尿病、膠原病、甲状腺機能亢進症、自律神経失調症、更年期障害などの疾患が根底にある場合や、向精神薬の副作用など薬剤性の多汗症もあります。精神的なストレスや緊張による交感神経の興奮が関係している場合もあります。
汗には、皮膚の表面にあるエクリン汗腺で作られるものと、毛穴の奥のほうに開いているアポクリン汗腺で作られるものがあります。アポクリン汗腺は思春期以降に発育し、たんぱく質の含有量が多いために独特の臭いがします。汗の臭いが強い場合は臭汗症と呼ばれます。とくにアポクリン汗の臭いが顕著なものを腋臭症(わきが)と呼びます。汗が皮膚表面に常在する細菌により分解されて生じた脂肪酸やアンモニアの臭いが、体臭の原因のひとつといわれています。
一般的な治療
治療には、薬物療法や外科的方法により対症療法的に発汗を抑える方法や、多汗症の根本的な原因を体質的に改善していく方法があります。
西洋医学では、塩化アルミニウム溶液などの外用薬を用いて汗腺を物理的に封じたり、発汗を促進する交感神経を注射薬でブロックしたりして(ボツリヌス毒素局所注射)、対症療法的に発汗を抑えます。手術によって交感神経を切断する治療法や、レーザーを照射して汗腺を焼き、汗腺を凝固する方法もあります。抗コリン薬や抗不安薬を用いて緊張と関連した発汗を減らすこともあります。
漢方薬による治療
漢方では、自律神経やホルモンのバランスを安定させ、あるいは心身のバランスをととのえ、多汗症や体臭の根本的な原因を体質的に改善することにより、多汗症・体臭・加齢臭の治療に当たります。漢方薬の働きにより自律神経やホルモンのバランスが整うと、過剰な発汗が減り、体臭が落ち着きます。体の内側から体質を変えていくことになります。
漢方では、汗は津液(しんえき)が変化したものと捉えています。津液とは、生命活動に必要な水液のことです。この津液や体温を調節する機能が衰えると、津液が過剰な汗として漏れ出て多汗症となります。体温調節機能が失調すると余分な熱がこもり、体臭が強まります。多汗や体臭は、津液や体温の調節をつかさどる五臓の肺、自律神経やホルモンのバランスをコントロールする五臓の肝(かん)、汗と関係の深い五臓の心(しん)などの機能失調により生じます。
体臭には熱邪(ねつじゃ)も深く関与しています。熱邪は、火熱により生じる症状を引き起こす病邪です。多汗や体臭は、熱邪による症状のひとつです。
このように、多汗症や体臭には「津液」と「熱邪」が深く関与しています。したがって漢方では、漢方薬で津液を調整し、熱邪を除去することにより、多汗症の治療を進めます。
(症例紹介ページもあります)
よく使われる漢方薬
漢方では、患者さん一人一人の体質や病状に合わせて処方を決めます。同じ汗や体臭の悩みでも、体質や病状が違えば効く漢方薬も異なります。一般には防已黄耆湯などが使われることがあるようですが、だれにでも効くわけではありません。以下に、汗や体臭の悩みに使われることの多い漢方薬を、みられることの多い体質とともに紹介します。患者さん一人一人の体質や症状に合わせて処方を決め、治療を進めるのが漢方治療の特徴です。
- ①柴胡加竜骨牡蛎湯
汗や体臭が精神的なストレスや緊張と関係しているようなら、漢方でいう「肝火(かんか)」という体質です。体の諸機能を調節し、情緒を安定させる働きを持つ五臓の肝の機能が、ストレスや緊張の影響によりスムーズに働かなくなって過剰な津液や熱邪を生み、多汗を生じさせます。手のひら、足の裏、脇の下、顔、頭など、局所的に汗をかきます。熱邪の影響で体臭が強まります。柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)などの漢方薬で、肝の機能の流れをスムーズにして肝火を鎮め、多汗症や体臭を治療していきます。
- ②知柏地黄丸、三物黄芩湯
慢性的な体調不良や過労、加齢、生活の不摂生などが関係しているようなら、「陰虚火旺(いんきょかおう)」という体質です。津液の不足により相対的に熱証が表れる体質です。体調不良や加齢により津液が消耗すると、相対的に熱邪が旺盛になり、この体質になります。熱邪の影響で体臭が強まります。寝汗をよくかきます。陰虚内熱(いんきょないねつ)ともいいます。知柏地黄丸(ちばくじおうがん)や三物黄芩湯(さんもつおうごんとう)などの漢方薬で、津液を潤して熱証を冷ますことにより、多汗症や体臭、加齢臭を改善していきます。
- ③竜胆瀉肝湯
べっとりと身にまとうような汗や体臭なら、「湿熱(しつねつ)」という体質です。過剰な湿気と熱が体内にこもりやすい体質です。この湿気と熱が、べとつく汗や体臭として表面化します。湿気と熱が体表から漏れ出て汗や体臭となるようなイメージです。この体質の場合は、竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう)などの漢方薬を用い、体内の過剰な湿気と熱を取り除くことにより、汗や体臭の悩みを改善していきます。
- ④桂枝加竜骨牡蛎湯
多汗とともに、疲労倦怠感、動悸、息切れなどがみられるようなら、「心気虚(しんききょ)」という体質です。五臓の心(しん)の機能が低下している状態です。漢方では「汗は心液である」といい、考えすぎや、心労の積み重ねにより、心の機能が衰えると発汗が増えます。この体質の場合は、桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)などの漢方薬を用い、心の機能を補うことで心の機能を強化し、多汗症を治療します。
- ⑤防已黄耆湯
全身からじわじわと汗をかく場合に多くみられるのは、漢方でいう「肺衛不固(はいえふこ)」という体質です。肺は五臓のひとつで、汗の分泌の調整をします。肺の機能が弱いと汗が漏れ出るのを防ぐことができず、必要以上に汗が出ます。ちょっと動いただけで汗が出たり、ちょっと暑いだけで汗ばんだりします。表衛不固(ひょうえふこ)ともいいます。防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)など、肺の機能を補う漢方薬を用い、多汗症を治療していきます。
ほかにも多汗症・体臭・加齢臭にみられる体質はたくさんあります。体質が違えば薬も変わります。自分の体質を正確に判断するためには、漢方の専門家の診察(カウンセリング)を受けることが、もっとも確実で安心です。当薬局では、漢方の専門家が一人一人の体質を的確に判断し、その人に最適な処方をオーダーメイドで処方しています。
予防/日常生活での注意点
日常生活では、皮膚を清潔に維持するためのスキンケアとともに、食事においては野菜を中心にして、肉類や刺激物の摂りすぎに注意しましょう。夜遅くの飲食も控えましょう。じゅうぶんな睡眠時間をとり、規則正しい生活を心がけてください。適度な運動を習慣づけるなどのストレス対策を日常に取り入れ、ストレスにより交感神経が優位にならないように生活習慣を改善しましょう。
(こちらの記事は「薬石花房 幸福薬局」幸井俊高が執筆・監修しました。日経DIオンラインにも掲載)
*執筆・監修者紹介*
 幸井俊高 (こうい としたか)
幸井俊高 (こうい としたか)
東京大学薬学部卒業。北京中医薬大学卒業。中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。「薬石花房 幸福薬局」院長。『医師・薬剤師のための漢方のエッセンス』『漢方治療指針』(日経BP)など漢方関連書籍を25冊以上執筆・出版している。日本経済新聞社の医師・薬剤師向けサイト「日経メディカル(日経DI:ドラッグインフォメーション)」や「日経グッデイ」にて長年にわたり漢方コラムを担当・連載・執筆。中国、台湾、韓国など海外での出版も多い。17年間にわたり帝国ホテル東京内で営業したのち、ホテルの建て替えに伴い、現在は東京・銀座で営業している。
あなたに合った漢方薬が何かは、あなたの証(体質や病状)により異なります。自分に合った漢方薬を選ぶためには、正確に処方の判断ができる漢方の専門家に相談することが、もっとも安心で確実です。どうぞお気軽にご連絡ください。
関連する記事を読む
- 寝汗の症例 (改善症例)
- 寝汗 (病気・症状)
- 多汗症・体臭・加齢臭(体験談) (改善症例)
- 不快なべっとり汗、緊張を漢方で克服 (ストーリー)
- 余分な汗が出る体質が漢方で治った! (ストーリー)