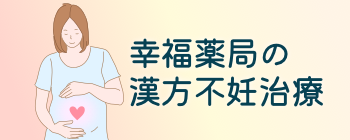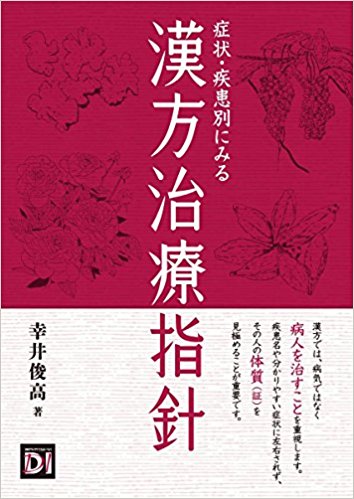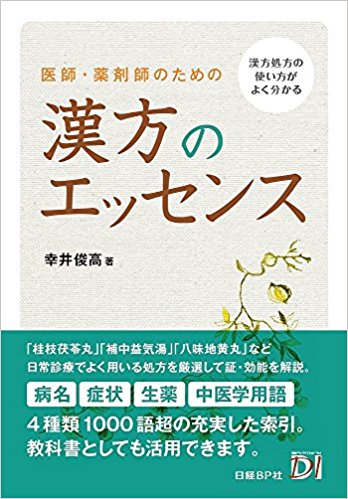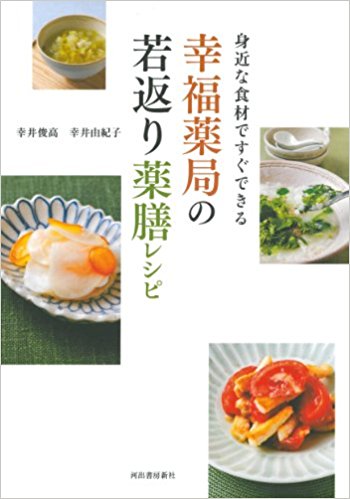副鼻腔炎(体験談)
(こちらの記事の監修:中医師 幸井俊高)
副鼻腔炎が漢方で治った体験談
副鼻腔炎が漢方薬で治った成功例を紹介します。漢方では、患者さん一人一人の体質に合わせて、処方を決めます。患者さん一人一人の体質に合わせて処方を決め、治療を進めるのが漢方治療の特徴です。
(こちらは症例紹介ページです。解説ページはこちら)
手術を勧められるほどの慢性副鼻腔炎を漢方薬で治療した症例

「長年の蓄膿症です。鼻づまりが強く、ときに粘っこく黄色い鼻水が出ます。病院で手術を勧められていますが、したくありません」
いつも頭が重く、ときどき痛みます。のどの痛みもあります。口がよく渇きます。舌は紅く、黄色い舌苔が付着しています。
この患者さんは、五臓六腑のひとつである肺(肺や鼻など呼吸をつかさどる臓腑)に熱邪(炎症など熱に似た症状を引き起こす病邪)が侵入している体質です。漢方でいう「肺熱(はいねつ)」という体質です。このため熱邪が副鼻腔に侵入して炎症を起こし、慢性副鼻腔炎になっているのでしょう。
この体質の場合は、漢方薬で肺の熱邪を除去して炎症を冷ますことにより、副鼻腔炎を治していきます。この患者さんには、辛夷清肺湯(しんいせいはいとう)などを服用してもらいました。服用を始めてから少しずつ症状が軽くなり、8か月で慢性副鼻腔炎を完治させることができました。手術を回避することもできました。
同じ慢性副鼻腔炎でも、精神的なストレスや感情の起伏などが関与しているようなら、漢方でいう「肝火(かんか)」という体質です。荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう)などの処方で、肝火を鎮めて熱や腫れを発散し、血行を改善して排膿し、副鼻腔炎を治療していきます。
黄色く粘っこい鼻水が多く、後鼻漏も生じているようなら、「熱痰(ねったん)」という体質です。痰も多く、鼻水や痰はすっきり排泄されません。咳も出ます。熱痰を排除する清肺湯(せいはいとう)などを用い、副鼻腔炎を治療します。
頭がぼうっとする慢性副鼻腔炎を漢方治療した症例
「慢性副鼻腔炎です。子どもの頃から鼻がすっきりしません。頭がぼうっとすることもあります。病院でネブライザー治療もしましたが、あまり効果は感じませんでした」
集中力が続かず、受験期には苦労しました。口がよく渇きます。鼻腔も乾燥しているように感じることがあります。口臭が気になります。舌は紅く、舌苔はほとんど付着していません。
この患者さんは、肺や鼻の粘膜の潤いが不足している体質です。漢方でいう「肺陰虚(はいいんきょ)」という体質に当たります。潤いの不足により相対的に熱が余って熱邪となり、副鼻腔炎が生じているのでしょう。頭がぼうっとする、集中力が続かない、口渇、鼻腔の乾燥、口臭、紅い舌、少ない舌苔などは、この体質の特徴です。
この体質の場合は、漢方薬で肺の潤いを補うことにより、慢性副鼻腔炎を治療します。この患者さんには、麦味地黄丸(ばくみじおうがん)などを服用してもらいました。1年間かかりましたが慢性副鼻腔炎を治療することができました。
頭がぼうっとする、集中力の低下などの症状が顕著でない場合は、麦門冬湯(ばくもんどうとう)などを使います。
急性副鼻腔炎の漢方治療症例
「かぜをひいたあと、鼻がつまっています。どろっとした鼻水がでます」
額のあたりと、両目の間が痛みます。まだ熱があります。病院で急性副鼻腔炎と診断されました。口が渇きます。舌は紅く、黄色い舌苔が薄く付着しています。
この患者さんは、外界からのウイルスや細菌などによる感染症(外感病といいます)で、漢方でいう「風熱(ふうねつ)」という状態です。かぜのあと副鼻腔に炎症が広がり、急性副鼻腔炎に罹患したのでしょう。とくに前頭洞(ぜんとうどう:額の裏にある副鼻腔)や篩骨洞(しこつどう:両目の間にある副鼻腔)に炎症が生じているようです。鼻づまり、粘っこい鼻水、痛み、発熱、口渇、紅い舌、薄く黄色い舌苔などは、この体質の特徴です。
この体質の場合は、風熱を発散させて除去する漢方薬を用います。この患者さんには、葛根湯加桔梗石膏(かっこんとうかききょうせっこう)などを服用してもらいました。この患者さんは、5日間の服用で急性副鼻腔炎を完治させました。
同じ外感病による副鼻腔炎でも、口渇はなく、悪寒がみられるようなら、漢方でいう「風寒(ふうかん)」という体質です。葛根湯加川芎辛夷(かっこんとうかせんきゅうしんい)など風寒を発散させて除去する漢方薬で、急性副鼻腔炎を治療します。
(こちらの記事は「薬石花房 幸福薬局」幸井俊高が執筆・監修しました。日経DIオンラインにも掲載)
*執筆・監修者紹介*
 幸井俊高 (こうい としたか)
幸井俊高 (こうい としたか)
東京大学薬学部卒業。北京中医薬大学卒業。中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。「薬石花房 幸福薬局」院長。『医師・薬剤師のための漢方のエッセンス』『漢方治療指針』(日経BP)など漢方関連書籍を25冊以上執筆・出版している。日本経済新聞社の医師・薬剤師向けサイト「日経メディカル(日経DI:ドラッグインフォメーション)」や「日経グッデイ」にて長年にわたり漢方コラムを担当・連載・執筆。中国、台湾、韓国など海外での出版も多い。17年間にわたり帝国ホテル東京内で営業したのち、ホテルの建て替えに伴い、現在は東京・銀座で営業している。
同じようなお悩みでお困りの方、漢方薬をお試しになりませんか?
あなたに合った漢方薬が何かは、あなたの証(体質や病状)により異なります。自分に合った漢方薬を選ぶためには、正確に処方の判断ができる漢方の専門家に相談することが、もっとも安心で確実です。どうぞお気軽にご連絡ください。
関連する記事を読む
- 血管運動性鼻炎(寒暖差アレルギー)(体験談) (改善症例)
- 血管運動性鼻炎(寒暖差アレルギー) (病気・症状)
- 後鼻漏(体験談) (改善症例)
- 後鼻漏 (病気・症状)
- 鼻炎の症例 (改善症例)
- 副鼻腔炎 (病気・症状)
- 厄介な鼻水・鼻づまりを漢方でスッキリ (ストーリー)
- 漢方で、花粉症でぐしゃぐしゃの顔と決別 (ストーリー)
- 花粉症の根治は体の中から変える (ストーリー)
- 鼻づまり (病気・症状)
- 花粉症 (病気・症状)
- 鼻炎 (病気・症状)