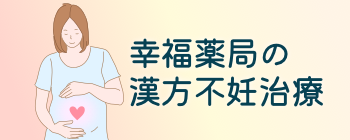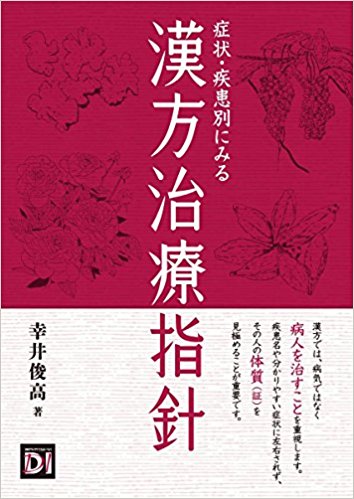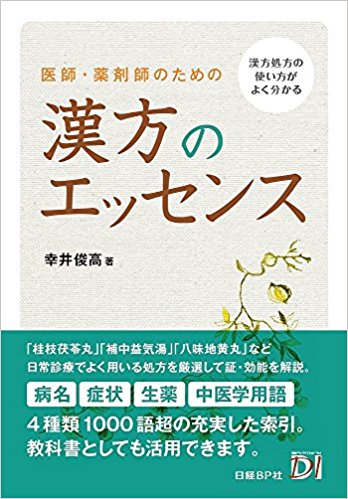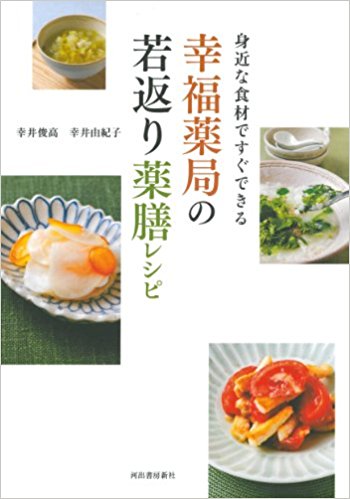後鼻漏(体験談)
(こちらの記事の監修:中医師 幸井俊高)
後鼻漏が漢方で治った体験談
後鼻漏が漢方薬で治った成功例を紹介します。漢方では、患者さん一人一人の体質に合わせて、処方を決めます。患者さん一人一人の体質に合わせて処方を決め、治療を進めるのが漢方治療の特徴です。
(こちらは症例紹介ページです。解説ページはこちら)
夜も不快だった後鼻漏を漢方治療して快眠を取り戻した症例

「仰向けに寝ると鼻水が喉に垂れてきて不快です。苦しくなることもあるので横を向いて寝るようにしていますが、それでも苦しかったり咳が出たりして夜中に目覚めることが多く、熟睡できません」
後鼻漏は粘っこく黄色い色をしています。よく鼻がつまります。そのせいか頭が重く、ときに痛みます。舌は紅く、黄色い舌苔が付着しています。
この患者さんは、五臓の肺に熱がこもっている体質です。五臓の肺は、呼吸をつかさどる臓腑で、鼻や喉などの器官は、この五臓の肺に含まれます。漢方でいう「肺熱(はいねつ)」という体質です。鼻腔などにこもった熱が炎症を引き起こし、後鼻漏が生じているのでしょう。粘っこく黄色い鼻水、鼻づまり、頭痛、頭重感、紅い舌、黄色い舌苔などは、この体質の特徴です。
この体質の場合は、漢方薬で肺熱を除去することにより、後鼻漏を治療します。この患者さんには、辛夷清肺湯(しんいせいはいとう)などを服用してもらいました。服用を始めて2か月後くらいから後鼻漏の色が薄くさらさらとしてきました。4か月目には後鼻漏がずいぶん減りました。その後も漢方を飲み続け、8か月後には後鼻漏に悩まされることはほとんどなくなりました。おかげで熟睡できるようになったと喜ばれました。
咳をともなう後鼻漏を漢方治療した症例
「長年、後鼻漏に悩んでいます。鼻水が喉に流れてきて不快です。後鼻漏が喉への刺激となって咳き込むこともあります」
鼻は、つまりがちです。鼻をかんでも鼻水は出ません。ときに動悸やめまいに見舞われます。舌は紅く、黄色い舌苔がべっとりと付着しています。
この患者さんは、痰飲(たんいん)という病理的産物が頭部に上昇して鼻腔内であふれ出しやすい体質です。痰飲とは、人体の基本的な構成成分のひとつである津液(しんえき:生命活動に必要な水液のこと)が、水分代謝の失調などにより異常な水液と化したものです。この体質を漢方では「痰濁上擾(たんだくじょうじょう)」といいます。痰飲が鼻腔内であふれ出したり粘膜に浮腫を生じさせたりすることにより、後鼻漏や咳き込み、鼻づまりが引き起こされているものと思われます。
この体質の場合は、痰飲を下降させて除去する漢方薬で、後鼻漏を治療します。この患者さんには、竹筎温胆湯(ちくじょうんたんとう)などを服用してもらいました。服用を始めて3か月後には咳き込むことがずいぶん減りました。10か月後には後鼻漏に悩まされることがなくなりました。
口臭をともなう後鼻漏の漢方治療症例
「昼も夜も後鼻漏に悩まされています。垂れてくる鼻水はねっとりとしており、やや黄色く、臭いがして不快です」
耳鼻科で副鼻腔炎と診断されました。抗生物質で治療すると一旦は改善しますが、しばらくすると再発します。乾いた咳が出ます。口臭も気になります。舌は紅く、舌苔はあまり付着していません。
この患者さんは、五臓の肺に必要な潤いや粘液が不足している体質です。漢方でいう「肺陰虚(はいいんきょ)」という体質です。潤いが足りないために熱を帯びやすく、炎症や口臭が生じています。黄色くねっとりとした臭いの強い鼻水、乾咳、口臭、紅い舌、少ない舌苔などは、この体質の特徴です。
この体質の場合は、漢方薬で肺の潤いを補うことにより、後鼻漏を治します。この患者さんには、麦味地黄丸(ばくみじおうがん)などを服用してもらいました。5か月後くらいから鼻水の色や臭いが気にならなくなってきました。8か月後には昼も夜も後鼻漏がほとんど出なくなりました。1年後に耳鼻科で検査したところ副鼻腔炎は完治していました。
(こちらの記事は「薬石花房 幸福薬局」幸井俊高が執筆・監修しました。日経DIオンラインにも掲載)
*執筆・監修者紹介*
 幸井俊高 (こうい としたか)
幸井俊高 (こうい としたか)
東京大学薬学部卒業。北京中医薬大学卒業。中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。「薬石花房 幸福薬局」院長。『医師・薬剤師のための漢方のエッセンス』『漢方治療指針』(日経BP)など漢方関連書籍を25冊以上執筆・出版している。日本経済新聞社の医師・薬剤師向けサイト「日経メディカル(日経DI:ドラッグインフォメーション)」や「日経グッデイ」にて長年にわたり漢方コラムを担当・連載・執筆。中国、台湾、韓国など海外での出版も多い。17年間にわたり帝国ホテル東京内で営業したのち、ホテルの建て替えに伴い、現在は東京・銀座で営業している。
同じようなお悩みでお困りの方、漢方薬をお試しになりませんか?
あなたに合った漢方薬が何かは、あなたの証(体質や病状)により異なります。自分に合った漢方薬を選ぶためには、正確に処方の判断ができる漢方の専門家に相談することが、もっとも安心で確実です。どうぞお気軽にご連絡ください。
関連する記事を読む
- 血管運動性鼻炎(寒暖差アレルギー)(体験談) (改善症例)
- 血管運動性鼻炎(寒暖差アレルギー) (病気・症状)
- 後鼻漏 (病気・症状)
- 鼻炎の症例 (改善症例)
- 副鼻腔炎(体験談) (改善症例)
- 副鼻腔炎 (病気・症状)
- 厄介な鼻水・鼻づまりを漢方でスッキリ (ストーリー)
- 漢方で、花粉症でぐしゃぐしゃの顔と決別 (ストーリー)
- 花粉症の根治は体の中から変える (ストーリー)
- 鼻づまり (病気・症状)
- 花粉症 (病気・症状)
- 鼻炎 (病気・症状)