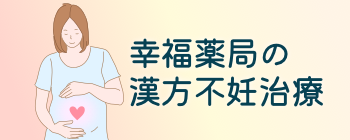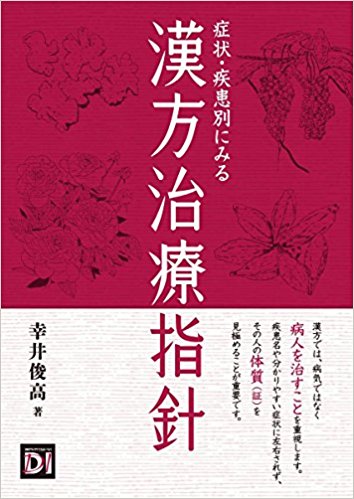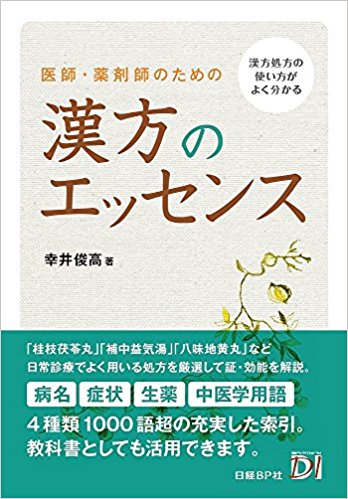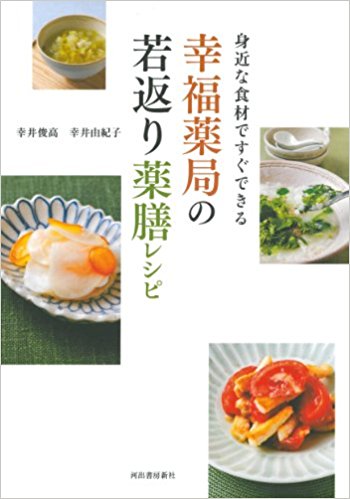過敏性腸症候群(IBS)(体験談)
(こちらの記事の監修:中医師 幸井俊高)
過敏性腸症候群が漢方で治った体験談
過敏性腸症候群が漢方薬で治った成功例を紹介します。漢方では、患者さん一人一人の体質に合わせて、処方を決めします。患者さん一人一人の体質に合わせて処方を決め、治療を進めるのが漢方治療の特徴です。
(こちらは症例紹介ページです。解説ページはこちら)
下痢と便秘を繰り返すタイプの過敏性腸症候群を治療した症例

「おなかの具合がよくなく、下痢と便秘を繰り返します。つねに腹部に不快感があり、下痢に悩まされる日が何日間か続いたと思うと、今度は便秘になります。しばらく便秘の状態が続いたあと、また下痢になります」
下痢のときは、急におなかが痛くなって下痢になります。便秘のときは、おなかが張って苦しい状態が続きます。排便したくてもなかなか出ません。やっと出ても、コロコロとしたウサギの糞のような便が申し訳程度に出るだけで、残便感がのこります。ふだんからストレスを感じやすくてイライラしやすく、ストレスが強いときに便通の調子もよくないように思います。舌は紅く、黄色い舌苔が付着しています。
この人はストレスや情緒変動の影響を受けて体調を崩しやすい体質です。漢方でいうところの「肝気横逆(かんきおうぎゃく)」という体質です。ストレスの影響を受けて気の流れが滞っており、そのために自律神経系が不安定になっています。その影響で大腸の蠕動運動が盛んになったり衰えたり、あるいは大腸がけいれんしたりして安定せず、便秘や下痢が生じ、混合型の過敏性腸症候群になっているようです。
このような場合は、漢方薬で気の流れをととのえていきます。気の流れが落ち着けば自律神経系も安定し、便通も安定していきます。
この体質に用いる代表的な処方は、逍遙散(しょうようさん)です。イライラや、怒りっぽいなどの症状が強いようなら、加味逍遙散(かみしょうようさん)を用います。
この患者さんには加味逍遙散を服用してもらいました。4か月ほどで下痢の症状がなくなりましたが、まだときどきコロコロした便が出るとのことでしたので、それ以降は四物湯(しもつとう)を一緒に服用してもらい、その3か月後にはすっかり体調がよくなり、漢方薬もやめてもらいました。
過敏性腸症候群で便秘をしている場合は、大腸の動きが弱っている場合が多いので、一般の下剤を使っても排便せず、かえっておなかが痛くなるだけに終わる場合もあります。通便作用がある地黄(じおう)や当帰(とうき)を含む四物湯あたりでやさしく対応してみるといいでしょう。逆に下痢ぎみならば、五苓散(ごれいさん)などを少し併用する場合があります。
下痢型の過敏性腸症候群を漢方治療した症例
「下痢型の過敏性腸症候群に悩まされています。ちょっとした緊張や不安でおなかが痛くなり、すぐトイレに行きたくなります。電車のなかや会議中など、いつどこで便意を催すかわからないので心配です」
もともと胃腸が丈夫なほうではありませんでしたが、大学受験のときにプレッシャーで頻繁に下痢をするようになりました。試験前や試験中におなかが痛くなり、すぐ便意を感じることが多くなりました。就職してからも、通勤電車のなかで急に腹痛に襲われることがあり、我慢できずに途中下車して駅のトイレに行くこともあります。
休日は、なんともありません。ふつうの便が出ます。寝ている間も腹痛は起こりません。便意で目覚めることもありません。舌は淡紅色で、白い舌苔が薄く付着しています。
この患者さんの場合は、緊張や不安、ストレスなどによる心理的な動揺が、下痢をする、しないという体調の変化に大きく影響しているのが特徴です。会社のストレスをあまり感じない休日や、ストレスを忘れていられる夜間には下痢になることはありません。
漢方では、心と体の関係を重視します。たとえば五臓の肝(かん)は、肝臓だけでなく、自律神経系や情緒活動をつかさどる機能ですが、この肝の機能バランスが失調すると、情緒不安定、イライラ、憂うつ感などの症状や、さらにさまざまな機能の失調が出現します。
この患者さんは、この肝の状態が不安定なようです。それが、もともと丈夫でない消化器系をつかさどる五臓の脾の機能を低下させ、ちょっとした緊張や不安で下痢しやすい体質になっているのでしょう。「脾虚肝乗(ひきょかんじょう)」という体質です。心身のバランスが安定しにくい体質ともいえます。
こういう場合は、漢方では消化器系の機能を高めつつ、ストレスを和らげていきます。処方は、桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう)などを使います。桂枝湯の芍薬の配合量を増やした処方ですが、そうすることにより、消化吸収機能を高めつつ、自律神経系を安定させてくれます。もし、疲れやすい、食欲にムラがあるなどの症状があれば、小建中湯(しょうけんちゅうとう)を用います。これは桂枝加芍薬湯に膠飴(こうい)を加えた処方で、消化吸収機能がさらに補われます。
ガス型の過敏性腸症候群の漢方治療症例
「ガス(おなら)のことで悩んでいます。おなかが張りやすく、とくに緊張したときに下腹部がぱんぱんに張ります。排ガスで楽になりますが、またしばらくすると、おなかが張ってきます。胃のあたりにも膨満感があり、この膨満感もげっぷが出ると楽になります」
ガス型の過敏性腸症候群です。おなかがよくゴロゴロと鳴ります。食後すぐにガスがたまります。今ではガスを我慢できないことも多く、食事中や会議中でもガスが出てしまいます。臭いや音が出るので周囲の人に気づかれてしまい、つらい思いをしています。映画館にも行けなくなりました。緊張が続くと胃の不快感や吐き気も生じます。舌は淡紅色で、微黄色の舌苔が付着しています。
この患者さんの場合、腸の症状と同時に胃の症状も出ています。このような体質を「脾胃不和(ひいふわ)」といいます。ストレスの影響で、下痢や吐き気など、胃と腸の症状が生じやすくなっています。ちょっとしたストレスや刺激でも胃腸が変調を起こしやすい体質なので、こういう場合は漢方薬で鎮静、整腸、健胃していきます。
代表的な処方は半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)です。胃を落ち着かせつつ、腸の機能を調整します。食生活の乱れや冷えが原因でこの証になる場合もあります。
今回はガス型の過敏性腸症候群に使いましたが、この処方は下痢型など、ほかのタイプにも使われます。過敏性腸症候群でありながら、げっぷ、吐き気などの胃の症状が同時にあるようなら、この処方を検討するといいいでしょう。
もし下痢の状態がひどい場合は甘草瀉心湯(かんぞうしゃしんとう)を、またガスのにおいが強い場合は生姜瀉心湯(しょうきょうしゃしんとう)を用います。それぞれ半夏瀉心湯をもとに加減された処方です。生姜瀉心湯は本来げっぷが臭い場合に用いられますが、ガスが臭い場合にも効果があるように思います。
(こちらの記事は「薬石花房 幸福薬局」幸井俊高が執筆・監修しました。日経DIオンラインにも掲載)
*執筆・監修者紹介*
 幸井俊高 (こうい としたか)
幸井俊高 (こうい としたか)
東京大学薬学部卒業。北京中医薬大学卒業。中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。「薬石花房 幸福薬局」院長。『医師・薬剤師のための漢方のエッセンス』『漢方治療指針』(日経BP)など漢方関連書籍を25冊以上執筆・出版している。日本経済新聞社の医師・薬剤師向けサイト「日経メディカル(日経DI)」や「日経グッデイ」にて長年にわたり漢方コラムを担当・連載・執筆。中国、台湾、韓国など海外での出版も多い。17年間にわたり帝国ホテル東京内で営業したのち、ホテルの建て替えに伴い、現在は東京・銀座で営業している。
同じようなお悩みでお困りの方、漢方薬をお試しになりませんか?
あなたに合った漢方薬が何かは、あなたの証(体質や病状)により異なります。自分に合った漢方薬を選ぶためには、正確に処方の判断ができる漢方の専門家に相談することが、もっとも安心で確実です。どうぞお気軽にご連絡ください。
関連する記事を読む
- 便秘の症例 (改善症例)
- 慢性的な下痢の症例 (改善症例)
- 過敏性腸症候群(IBS) (病気・症状)
- 便秘体質を改善して、下剤とさようなら (ストーリー)
- がんこな便秘もあきらめないで (ストーリー)
- 気持ちをゆるめて過敏性腸症候群を緩和 (ストーリー)
- 下痢 (病気・症状)
- 便秘 (病気・症状)