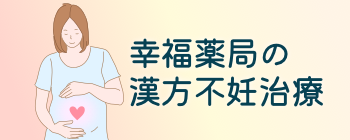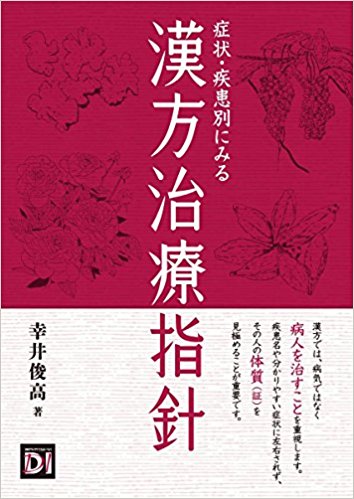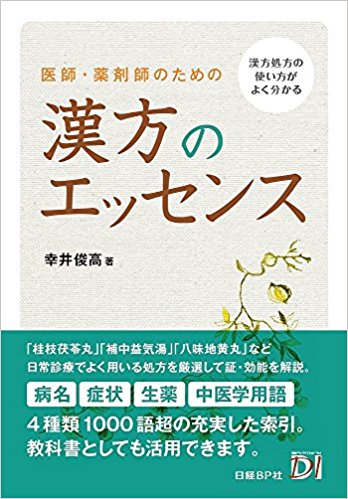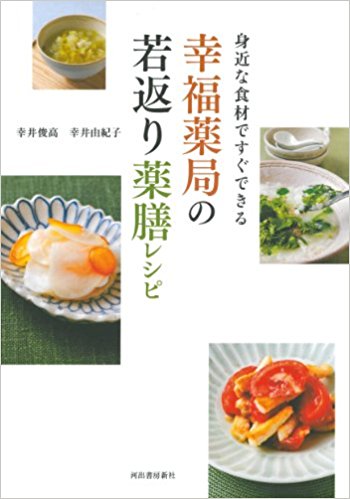過敏性腸症候群(IBS)
(こちらの記事の監修:中医師 幸井俊高)
過敏性腸症候群(IBS)に効く漢方薬
過敏性腸症候群(IBS)の漢方治療について解説します。一般にはお薬の力で腹痛や下痢などの症状を抑える治療が行われますが、再発したり完治しなかったりすることが多い病気です。漢方薬としては桂枝加芍薬湯がよく使われるようですが、これも体質が合わないと効きません。当薬局では、患者さん一人一人の体質に合わせて漢方薬を処方し、過敏性腸症候群の根本治療を進めています。
*目次*
過敏性腸症候群(IBS)とは
症状
原因
一般的な治療
漢方薬による治療
よく使われる漢方薬
予防/日常生活での注意点
(症例紹介ページもあります)
過敏性腸症候群(IBS)とは

過敏性腸症候群(IBS)は、腸(おもに大腸)の運動や分泌の機能異常により生じる病気の総称です。一般に検査をしても異常は見つかりませんが、腹痛、下痢、残便感、ガス(おなら)、便秘など、便通や下腹部の不調が現れます。症状によって下痢型、便秘型などに分類されます。
症状
快食、快眠、快便は元気のバロメーターだとよく言われます。おいしく食べて、ぐっすり寝て、すっきり排便できていれば、まずは健康だという意味です。毎日、朝の目覚めが爽やかで、食事の前にはちゃんとおなかが空いて、健康的な便がスッキリ出てくれれば、体調だけでなく、気分も爽快です。
ところが腸の調子がよくないと、バナナ状の便がスッキリとはなかなか出てきてくれません。慢性的に下痢ぎみだったり、逆に便秘症でコロコロとウサギの糞のような便しか出なかったり、あるいはガスがたまって下腹がパンパンに張ってしまったりと、下痢、残便感、腹痛、腹部不快感、便秘、ガス(おなら)、腹部膨満感などの症状が現れます。
通勤や通学の途中でおなかが痛くなって途中下車する、いつ下痢に襲われるか心配で急行電車に乗れない、会議中や授業中におなかが痛くなるなど、生活や仕事に支障をきたす場合も少なくありません。
過敏性腸症候群は症状によって下痢型、便秘型、混合型(交替型・不安定型)、ガス型、分泌型などに分類されます。混合型は下痢になったり便秘になったりするタイプで、分泌型とは強い腹痛のあと粘液が排泄されるタイプです。
原因
現代医学的には、腸の運動をつかさどる自律神経系の異常や、精神的なストレス、不安、過度の緊張などが原因と考えられています。暴飲暴食やアルコール類の飲みすぎ、喫煙、不規則な生活、過労などが原因となる場合もあります。大腸の蠕動(ぜんどう)運動が盛んになりすぎたり、大腸がけいれんしてしまったりすると、下痢や便秘、ガスがたまる、といった症状が現れます。
一般的な治療
過敏性腸症候群の治療には、薬の力で人工的に症状を抑える治療と、腸の働きをととのえて自然な排便ができるように体質改善を進める治療とがあります。西洋医学では、おもに薬物療法が行われ、薬の力で不快な症状を抑えます。使われることが多いお薬は、腸管の内容物を調整する高分子重合体(コロネルなど)や、腸の運動をととのえる薬(イリボーなど)、下痢を止める薬(ロペラミドなど)、便秘を改善する薬(酸化マグネシウム、ガスチモンなど)、整腸剤(ミヤBMなど)、抗不安薬、抗うつ薬などです。
漢方薬による治療
漢方では、過敏性腸症候群を、五臓の脾(ひ)や肝(かん)の機能失調と関連が深い疾患と捉えています。脾は五臓のひとつで、消化吸収をつかさどります。したがって腸はここに含まれます。また肝も五臓のひとつで、情緒や諸機能の調整をつかさどります。蠕動運動などの腸の機能の調整も、この肝が行います。ストレスや環境変化により失調しやすい臓腑です。
この五臓の脾や肝の機能が失調したとき、過敏性腸症候群が生じます。したがって漢方では、おもに五臓の脾や肝の失調を治療することにより、過敏性腸症候群の治療を進めます。
過敏性腸症候群はストレスと深い関係にあります。漢方では、心と体は切っても切れない関係にあるということを重視しており、これを「心身一如(しんしんいちにょ)」といいます。過敏性腸症候群のようにストレスと関係の深い病気の治療には、この漢方の考え方が有効です。
過敏性腸症候群の場合は、脾の機能をととのえておなかを丈夫にし、肝の機能をととのえてストレスに強くなることにより、体質を改善し、過敏性腸症候群を治療していきます。
(症例紹介ページもあります)
よく使われる漢方薬
漢方では、患者さん一人一人の体質や病状に合わせて処方を決めます。同じ過敏性腸症候群という病名でも、体質や病状が違えば効く漢方薬も異なります。使われることが多い処方に桂枝加芍薬湯がありますが、だれにでも効くわけではありません。以下に、過敏性腸症候群に使われることの多い漢方薬を、この病気にみられることの多い体質とともに紹介します。患者さん一人一人の体質や病状に合わせて処方を決め、治療を進めるのが漢方治療の特徴です。
- ①四君子湯
胃腸機能が弱いためにちょっとした刺激で下痢や便秘になりやすいようなら、漢方でいう「脾気虚(ひききょ)」という体質です。消化器系の機能が弱い体質です。体力的にも丈夫でない人が多く、消化不良ぎみです。こういう体質の人に対しては、四君子湯(しくんしとう)など、胃腸機能を丈夫にする漢方薬を使って過敏性腸症候群の治療を進めます。
- ②半夏瀉心湯、甘草瀉心湯、生姜瀉心湯
ストレスや食生活の乱れ、冷えなどの影響で下痢や吐き気が生じやすくなっているようなら、「脾胃不和(ひいふわ)」という体質です。ちょっとしたストレスや刺激でも胃腸が変調を起こしやすい体質なので、こういう場合は半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)、甘草瀉心湯(かんぞうしゃしんとう)、生姜瀉心湯(しょうきょうしゃしんとう)など、胃腸の機能をととのえる漢方薬で鎮静、整腸、健胃し、過敏性腸症候群を治していきます。
- ③逍遙散、加味逍遙散
ストレスや情緒変動の影響が強い場合は、「肝気横逆(かんきおうぎゃく)」という体質です。ストレスや情緒変動の影響で気の流れがわるくなり、そのために自律神経系が失調し、便秘や下痢が生じやすくなっています。逍遙散(しょうようさん)、加味逍遙散(かみしょうようさん)などの漢方薬で、気の流れをととのえて過敏性腸症候群を治療していきます。
- ④桂枝加芍薬湯、小建中湯
もともと消化器系が丈夫でないところに緊張や不安が乗じて腹痛や下痢が生じている場合は、「脾虚肝乗(ひきょかんじょう)」という体質です。もともと消化器系が丈夫でないために肝(自律神経系など)の機能を制御できず、ちょっとした緊張や不安で体調を崩しやすい体質です。心身のバランスが安定しにくい体質ともいえます。漢方では、桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう)、小建中湯(しょうけんちゅうとう)などの漢方薬を用い、消化器系の機能を高めつつ、ストレスを和らげていくことにより、過敏性腸症候群を治していきます。
ほかにも過敏性腸症候群にみられる体質はたくさんあります。体質が違えば薬も変わります。自分の体質を正確に判断するためには、漢方の専門家の診察(カウンセリング)を受けることが、もっとも確実で安心です。当薬局では、漢方の専門家が一人一人の体質を的確に判断し、その人に最適な処方をオーダーメイドで処方しています。
予防/日常生活での注意点
日常生活では、暴飲暴食を避けてください。とくに脂質や炭水化物、香辛料などの刺激物が多い食事、アルコール類、カフェインを含んだ飲料、乳製品、おなかを冷やす飲食物などで症状が悪化する可能性がありますので注意が必要です。とくに夜間の暴飲暴食は避けましょう。タバコも控えたほうが賢明です。さらにストレスをためない工夫をしつつ、じゅうぶんな睡眠をとり、規則正しい生活や適度な運動を心がけましょう。
(こちらの記事は「薬石花房 幸福薬局」幸井俊高が執筆・監修しました。日経DIオンラインにも掲載)
*執筆・監修者紹介*
 幸井俊高 (こうい としたか)
幸井俊高 (こうい としたか)
東京大学薬学部卒業。北京中医薬大学卒業。中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。「薬石花房 幸福薬局」院長。『医師・薬剤師のための漢方のエッセンス』『漢方治療指針』(日経BP)など漢方関連書籍を25冊以上執筆・出版している。日本経済新聞社の医師・薬剤師向けサイト「日経メディカル(日経DI)」や「日経グッデイ」にて長年にわたり漢方コラムを担当・連載・執筆。中国、台湾、韓国など海外での出版も多い。17年間にわたり帝国ホテル東京内で営業したのち、ホテルの建て替えに伴い、現在は東京・銀座で営業している。
あなたに合った漢方薬が何かは、あなたの証(体質や病状)により異なります。自分に合った漢方薬を選ぶためには、正確に処方の判断ができる漢方の専門家に相談することが、もっとも安心で確実です。どうぞお気軽にご連絡ください。
関連する記事を読む
- 過敏性腸症候群(IBS)(体験談) (改善症例)
- 便秘の症例 (改善症例)
- 慢性的な下痢の症例 (改善症例)
- 便秘体質を改善して、下剤とさようなら (ストーリー)
- がんこな便秘もあきらめないで (ストーリー)
- 気持ちをゆるめて過敏性腸症候群を緩和 (ストーリー)
- 下痢 (病気・症状)
- 便秘 (病気・症状)